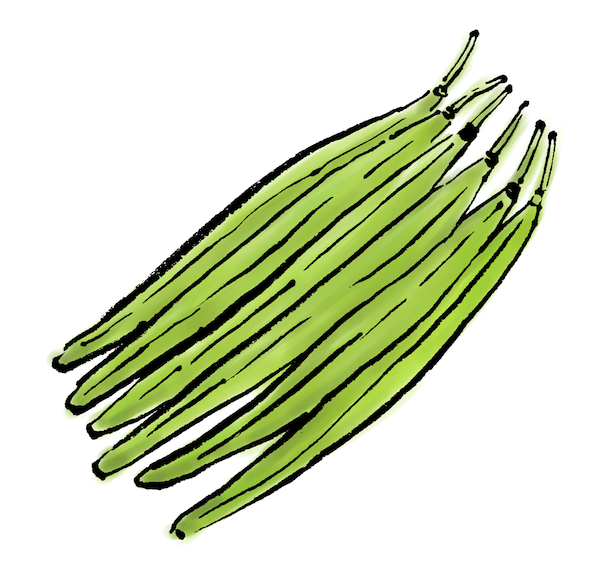第一話
日曜の朝、小鳥のさえずりが聞こえている。
翔くん麗ちゃんは仲の良い兄妹だ。朝ご飯の後、おしゃべりをしている。
「インゲン豆って、どうしてこんなにおいしいんだろうね?」
「お母さんがお料理上手だからでしょ」
「麗ちゃん、インゲン豆って外国から来たんだよ。知ってたかい?」
「そんなはずないわよ。インゲン豆は日本のものよ。日本の」
「じゃあ、おじいちゃんに聞きに行こうか?」
「いいわよ!でも、きっとお兄ちゃんの負けよ!」
おじいさんが、笑いながらやって来た。
「聞いたぞ聞いたぞ。麗ちゃんも翔くんも可愛いね。でもね、インゲン豆はね、種は外来のものだが、日本で育ったんだ。トマトと同じだよ。だってトマトという呼び方自体、外来語だろう?」
「そうなのかあ。じゃ、引分けにしようか」と翔くん。
でも、麗ちゃんはまだ納得できない。
「ちがうわよ。ちがう!トマトはトマト、インゲンはインゲンでしょ。おじいちゃん、助けてよ」
おじいさんは、ちょっと涙目になった麗ちゃんを抱き寄せた。
「そうだね。麗ちゃんの言うことももっともだ。実はね、インゲン豆の「インゲン」というのは、もともと、京都にある萬福寺というお寺をつくった有名な和尚さんの名前からきたんだよ」
「ぼくは覚えているよ!前におじいちゃんが京都に連れていってくれたときに、インゲン禅師様という名前を聞いたことがあるもの!」
「わたしはお兄ちゃんのお話じゃなく、おじいちゃんのお話を聞きたいの!」
麗ちゃん、ますます気合が入ってきたようだ。
おじいさんは、可愛い孫たちを見て目を細め、孫たちにもっと近く、椅子に座るよう手招きした。そして孫たちが真向いのソファに腰掛けると、語り始めたのだった。
「つまりね、種は外来だが日本で育った、ということなんだよ」
ところが麗ちゃん、急に椅子から躍り上がると、
「おじいちゃん、ちょっと待っててね、すぐ戻ってくるから!」
言うなり、どこかへ飛んで行ってしまった。
すると翔くんまで何か思い出したかのように、「そうだ、ぼくもちょっと」と部屋を出ていってしまった。
おじいさんはソファに座ったまま、開いた口が塞がらない。
****** ****** ******
陽射しが明るく、相変わらず小鳥のさえずりが聞こえている。
「戻ってきたよ!」
麗ちゃんの声は小鳥より可愛らしい。
お母さんの手を引きながら、戻ってきた。お母さんは急いでエプロンを外し、手を拭い、ほほえみながらソファに腰を下ろした。
「待ってよ、待って!」
翔くんも転がるようにしてやってきた。翔くんの後ろには、満面汗をしたたらせ、作業着を着込んだお父さんがいる。
おじいさんにも、ようやく呑み込めた。二人は「票集め」をしていたのだ。おじいさんは、こうなれば今日はこのインゲン豆物語を何としてもしっかり話さなければならないと思った。
「インゲン豆の物語はね、四百年前の中国から始まるんだよ」
おじいさんは、お茶に少し口をつけてから話し始めた。
「その頃の中国は「明」と言った。本では「明朝」とも記されているはずだ。ちょうど日本の江戸時代にあたる」
おじいさんは後ろの本棚から、地図本を引っ張り出す。本を開け、
「ほら、ここだ。東シナ海。このあたりの海から遠くない村に、翔くんと麗ちゃんのような二人の子供がいたんだ」
翔くんと麗ちゃんがおじいさんの傍に座りなおした。おじいさんが、笑って二人の頭を撫でる。
「でもね、その二人の子供は、兄妹じゃないよ。男の子の名前は「昺」。家はとっても貧しかった。女の子は「梅」といって、裕福な家の娘さんだった。でも、二人はとても仲が良く、いつも楽しく遊んでいたんだ」
「何をして遊んでたの?」と麗ちゃん。
おじいさんは、片目をつぶり、思わせぶりに、
「養蚕だよ、ぷっくりしたお蚕様だよ」と答えた。
「それって、なに?」
麗ちゃんと翔くんが異口同音に言う。すると、お母さんが笑いながらシルクのハンカチを取り出した。そしてハンカチを指しながら、
「お蚕様が「大人」になると、糸を吐くの。そして、人がその糸をシルクにするのよ」と教えてあげた。
「面白いわ!」
麗ちゃんが躍り上がって、お母さんのハンカチを手に取った。触れながら、なめらかな手触りにうっとりしている。
「ふん、女の子のものだよな」と翔くん。
「いやいや、これはすごいものなんだよ。飛行機にだって使われてる。「シルク」とも言うんだ」お父さんも話の輪に入ってきた。
「そうだね。それにシルクロード。この日本まで通じていた文明の道、文化の道だった。群馬県の、いまじゃ世界遺産にもなっている冨岡製糸場にも関係するんだよ」おじいさんが言った。
第二話
麗ちゃんが夢中になってきた。
シルクロードの話にはなにかロマンがいっぱい詰まっているような気がしたのだ。早く先を語るよう、おじいさんにせがむ。
「でも、それがインゲン豆とどういう関係があるの?」翔くんがたずねる。
「いい質問だね。おじいちゃんもね、子供の頃、わたしのおじいさんにこの質問をしてみたんだ。でもね、そのときは昺ちゃんに聞いてみないとね、と言われたんだよ」
「それで、おじいちゃん、聞きに行ったの?」と麗ちゃん。
「馬鹿だな!四百年前の人にどうやって聞くのさ」翔くんがグサリと一言。
おじいさんは大笑いしたが、地図本をぽんと叩くと、
「聞いたよ、聞いた。本の中に全部書いてあるからね」と言った。
二人の孫の顔に微笑みがひろがった。
「わたしは、一生懸命に本を読んだ。それでやっと分かったんだ。男の子の昺ちゃんの苗字は林で、名前は曽昺といった。だから、「林曽昺」というのが本当の名前で、「昺ちゃん」というのは彼の幼名なんだよ。子供のころの呼び名だ。それで、村の子供たちは、彼を「昺ちゃん」と呼んでいた。裕福な家のお嬢さんとして生まれた梅ちゃんは、きっと「昺兄ちゃん」と呼んでいたことだろう」
おじいさんはここで、思い切りか細い声で梅ちゃんの声を真似、「昺兄さん—–」と言ってみた。孫たちは大笑いした。傍にいたお父さんとお母さんまで思わず吹き出してしまった。
麗ちゃんはひとしきり笑った後、また尋ねた。
「じゃあ、梅ちゃんの本当の名前は何というの?」
「梅ちゃんの苗字は「黄」、名前は「幽梅」といったんだ」
「黄幽梅。なんて雅なお名前でしょう!」とお母さん。
「それはそうだよ。黄家は名家だもの。歴史に名を残した大軍師が、彼女のお兄さんだ」とお父さん。
「お父さん、その大軍師の名前も知ってるの?」と翔くん。
「知っているよ。大軍師黄道周。中国の歴史に関心のある人ならかなり知られた名だからね。」
「じゃあその人とインゲン豆はどうつながるの?」と麗ちゃん。
「そうだよ。おじいちゃんがさっき言ってたインゲン豆の「インゲン」は京都の有名な和尚さんでしょ?でもそれは昺ちゃんの話と関係ないじゃない?」
翔くんもまだまだわからない。
「いや、関係が大有りなんだ。だってね、実はその昺ちゃんがインゲンなんだ。インゲンはその昺ちゃんなんだよ。だから、昺ちゃんとインゲンは関係大有りなのさ!」お父さんが助け舟を出した。
翔くんと麗ちゃんは、聞きながらずっと目をしばたたかせていた。まるで、沢山のクエスチョンマークに囲まれてしまったかのよう。おじいさんがその様子を見て、優しく、ゆっくり言った。
「お父さんの言った通りなんだよ。その後、昺ちゃんはお坊さんの隠元(インゲン)禅師様になった。インゲンと昺ちゃんは同じ人なんだ。インゲン豆と昺ちゃん、梅ちゃん、黄道周大軍師にはそういう関係があったんだよ」
「なるほど。そうだったのか」翔くんが納得した。
だが、麗ちゃんは相変わらず目をパチクリさせている。
「でも、それなら昺兄さんはどうしてお坊さんになったの?」
「大丈夫、大丈夫。ちゃんとお坊さんになれるから。でも、あなたたちは、そろそろご飯を食べる時間よ。それに、おじいちゃんにもちょっとお休みをあげないとね」お母さんがここで、一旦の事態収拾に動いた。
おじいさんも笑顔で頷いた。
「うん、わかった。じゃ、インゲン豆を食べに行こう!」
兄妹はおじいさんと手をつないで、ダイニングに向かった。
****** ****** ******
その日の午後、おじいさんは客間で電動マッサージの椅子に身を預け、体を伸ばしていた。時折いびきの音が高くなったり低くなったりしている。
翔くんと麗ちゃんが抜き足差し足で祖父のそばに来て、腰を下ろした。
彼らが動いた時に、あるいは音がしたのかもしれない。
おじいさんのいびきが止まった。
翔くんが手を振り、麗ちゃんがうなずく。
「なにかの暗号かい?見えたよ。」
おじいさんはにっこりして起き上がり、語り部のソファのほうに移った。
兄妹も椅子をソファの傍らに移し、じっとおじいさんの顔を見つめている。
「さっきね、夢を見たんだよ。その夢、教えてあげようか?」
兄弟はもう、待ちきれない。いきなり拍手だ。
おじいさんはすこし座り直し、語り始めた。
「さっき居眠りしてた時にね、おじいちゃん、子供に戻ったような気がしたんだ。そしてね、四百年前の明の国の海辺を走っていたんだ。昺ちゃんの家にも入ったんだよ。きれいに切り整えた茅葺でふいた家だったな。でも、とても粗末な家だった」
「昺ちゃんには二人のお兄さんがいて、彼は末っ子だった。おじいさんはね、まるで三人のうちの一人になったような感じだった。わたしはずっと昺ちゃんの後ろにくっ付いていった。彼が向かうところに、私も行ったんだよ」
第三話
夢の中で、おじいさんは、昺の後ろに付いて、茅葺の家から出た。どこに行くのかは、さっぱり分からない。ただ、昺がお蚕の入った木の箱を持っているのが見えた。
箱の中のぷっくりしたお蚕様が、もうすぐ桑の葉を食べ終わるころだ。
彼の家の斜め向かいに、とてもおおきな広いレンガづくりの家があった。白壁に青い瓦を葺いている。みるからに豪奢な造りだ。
まもなく大きな黒塗りの門から、きれいな服を着た女の子が「昺兄ちゃん―」と名を呼びながら、とびはねるように出てきた。斜向かいに住む黄家の息女、黄幽梅。昺の幼馴染で、仲良しの梅ちゃんだ。
梅が蚕の箱を指さしながら、
「昺兄ちゃん、お蚕様もうすぐ糸を吐くわね」と言った。
「ほら、桑の葉をもう食べ終えた。もう糸なんか吐かないよ」と昺。
「それならわたしに付いてきて!」梅はそう言うなり昺の手を引き、黄家の門をくぐっていった。
****** ****** ******
「おじいちゃん、おじいちゃん!おじいちゃんも一緒に入ったの?」
麗ちゃんが夢中できいた。
おじいさんはここで悪戯っぽく目配せし、わざと溜息をもらして言う。
「いやあ、残念だったな。わたしがまさに黄家に入ろうとしたとき、麗ちゃんと翔くんが騒いだもんだから目が覚めちゃったんだよ」
「お兄ちゃんだよ、お兄ちゃんが悪いんだよ!」と麗ちゃん。
「冗談なだけだよ」翔くんが笑った。
「そういうこと。おじいちゃんは麗ちゃんと翔くんのどっちが賢くて、どっちの気立てがいいのか知りたかったの」
おじいさんは、そう言いながら、やさしく麗ちゃんの頭をなでた。
「麗ちゃんは、とっても純粋だね。おじいちゃんは大好きだよ。実はね、さっき話した夢も、インゲン豆物語のなかのお話なんだよ」
麗ちゃんに笑顔が戻った。おじいさんのそばに寄り添って、
「おじいさんは物語が上手だね。わたしおじいさんが話す物語の中に入ってしまったみたい。それで、そのあと、昺兄ちゃんは桑の葉を見つけたの?」
このとき、お母さんがお茶を持ってきた。
おじいさんも喉が乾いていた。「ありがたいな」と言って飲み干した。
「もちろん見つけたさ。黄家の庭には大きな桑の木があるからね。桑の葉がいっぱいあるんだ」
おじいさんはお母さんに腰掛けるよう手招きをし、話を続けた。
昺は、するする木を登ると、ポケットにいっぱい葉っぱを採った。後ろを振り向き、梅に笑いかけた。
そのとき、この木から遠くないところに色鮮やかな豆畑があるのを見つけた。
機転の利く翔くんがすぐさま応じた。
「インゲン豆でしょ。おじいちゃん。インゲン豆でしょ!」
おじいさんは感心した素振りを見せて、言った。
「そのころはね、「四季豆」といったんだよ。中国の南方は温暖な気候だからね。
豆が一年を通して収穫できるのさ」
麗ちゃんの大きな瞳を見開き、おじいさんを見上げ、またお母さんを見やる。またもや頭の中にたくさんのクエスチョンマークが出てきたようだ。
お母さんが、麗ちゃんと翔くんにそっと言う。
「そうよ。おじいちゃんの言われる通り。そのころは昺ちゃんもまだお坊さんになってないでしょ。インゲン(隠元)というお名前になっておられないのだから、まだインゲン豆、ではなかったの」
「うん、わかった。でもインゲン豆は四季豆、なんでしょう。言い方が違うだけでしょ」と麗ちゃん。
まだよくわかっていないようだ。
「ぼくはわかったよ。つまり昺ちゃんが有名な隠元禅師様になってから、四季豆も有名なインゲン豆になったというわけだよね」
翔くんが自信満々に言った。
「じゃあ、どうやって変わったか分かるの?」
麗ちゃんはまだまだ引き下がらない。
「トランスフォーマーみたいなもんさ。変われ、といえば変わるんだよ!」
麗ちゃんが、椅子から立ち上がる。
「でたらめよ。でたらめだわ!」
おじいさんは笑いながら麗ちゃんを椅子に座らせた。この時、お父さんも来て、おじいさんのそばに座った。
「いいかい。みごとな偶然に恵まれなければ、物語は作れないのだよ。いや、縁、と言った方がいいかな。わたしはね、昺ちゃんがどうやって有名な隠元禅師様になったのかを君たちに伝えたいんだ。お父さんも来たから、梅ちゃんのお兄さん、黄道周がどうやって有名な大軍師になったのか、お話ししよう」
おじいさんが身を乗り出すようにしてそう言った。
「それから、隠元禅師様と大軍師がどうやって仲良しになったのかも」
お父さんがちょっと勿体をつけて言った。
「あとは、昺ちゃんと梅ちゃんが大人になった後に、どうなったのか」
お母さんまで加わってきた。
「すごいすごい!早くお話して!」
翔くんと麗ちゃん、待ちきれなくなってきた。
第四話
昺の家は、とても貧しかった。そのため昺のお父さんは出稼ぎで遠くの町まで出かけねばからなかった。お母さんは昺たち三人兄弟の世話をしながら、毎日辛い野良仕事に精を出していた。
春は、田植えの季節だ。
昺ら三人兄弟が並んで鋤(すき)を引き、お母さんが後ろで重い鋤を支え、耕している。
じりじりと照りつける太陽。足元には泥土。汗びっしょりのお母さんが、突然倒れてしまう。
茅葺(かやぶき)のあばら家で、お母さんが身体を横たえている。
昺は三人兄弟の末っ子だが、一番の元気者だ。彼が年長の兄たちの面倒を見ながら母親を守っているといっていい。
やがて、昺はお父さんを探しに行こうと決心した。
お母さんは、力なくうなずくしかなかった。それでも精一杯の元気を振り絞り、「早く帰ってきて」と声をかけた。
昺は、北に向かった。故郷の福清から福州まで。さらに、省を跨いで浙江省まで足を延ばした。
道すがら、親戚の家を訪ねてみたが、父親の消息はわからなかった。
歯を食いしばり、とにかく、前に進むしかなかった。
物乞いまでして、生を繋(つな)いだ。
しかし、銭塘江に辿り着けば、あとは茫漠たる大海原だ。もう、昺にはなすすべがなかった。
このとき、海岸で遊んでいた裕福な家の子供たちが、ぼろぼろの服をまとっている昺を見つけた。まさに、格好の標的だった。
いじわるな子供たちが、砂をつかんでは、昺に投げつける。
はやし立て、あちらへこちらへ追いかけては、小突き回した。
昺はやがて、波打ち際の岩場まで追い詰められてしまった。
昺の足元で、波しぶきが飛び散る。
遠くの水平線を見やり、思わず、「お父さん、どこにいるの!どこにいってしまったの?」と、虚空に向け、叫んだ。
悲しみに満ちた声が、海と空に響いた。
一人の僧侶が、昺の叫びを聞いていた。
彼は海岸に駆けつけると、いじわるな子供たちを追い払った。岩場に向かい、昺を助け起こし、そっと、瞳の涙を拭(ぬぐ)う。
海が、果てしなく広がっている。
その海と空の境に、ぼんやりと島嶼(とうしょ)が見えた。
夢幻のような彩雲が、島をより神秘的にみせていた。
遠くからみると、まるで仙境のようだった。
僧侶は島を指さし、あそこが仏教の聖地「普陀山」だ。わたしはその普陀山の観音寺から来たのだよ、と昺に語りかけた。そして昺に、自分と一緒に行きたいかと、たずねた。
「行きます。行きたいです!」
昺は、「観音」の二文字を聞くなりそう答え、鼻を拭いた。
「それでは、いっしょに行こう!」
僧侶は、錨を上げていた一艘の漁船を見つけ、昺を伴い、そちらに向かった。そして船頭と二言三言ことばを交わすと、船上の人となった。
僧侶と昺は、船べりで身を寄せ合った。
海風と頭上を舞うカモメから祝福を受け、二人は「観音」の聖地である普陀山へと向かった。
****** ****** ******
「普陀山の観音寺というところが、昺ちゃんが初めて仏門に入ったところなんだよ。そしてこの和尚さんが、その後、昺ちゃんの先生となる費通師父なんだ」
麗ちゃんは、物語に引き込まれていた。
「費通師父ってほんとうにやさしい人。昺ちゃんは運がいいね」とつぶやいた。
でも、翔くんは昺がこんなに遠くまでやってきたそもそもの動機を覚えていたから、気ぜわしげにきいた。
「昺ちゃんは、その後、お父さんを探し出せたの?」
「費通師父と出会えたのは、お父さんを探し出すよりずっといいことだったと思うよ」と、おじいさん。
「どうして、お師匠さんがお父さんより大事なの?」今度は、麗ちゃんだ。
「それはね、昺ちゃんが、偶然のようにみえるけど、費通師父と出会い、その後仏門に入り、人の世の「大愛」を見つけたからだ。大愛は、両親の愛の百倍も大きいのだよ」
「じゃあ、おじいさんの愛と比べたらどうなの?」
「千倍は大きいだろうね」
「それじゃ、先生の愛と比べたら?」と翔くん。
「おやおや、まるで算数の問題のようになっちゃったね。明日学校に行ったら、算数の先生にきいてごらんよ」
おじいさんは、優しく微笑むのだった。
第五話
学校は、家から遠くない。
今日、翔くんはいつもより早く学校に行った。学校に着くなり職員室に直行し、算数の先生にお辞儀をして、「先生、おはようございます。先生に聞きたいことがあるんです。世の中の大愛とは、なんですか?」と、いきなり切り出した。
算数の先生はメガネを外し、拭きながら、
「その質問はね、たぶん国語の先生に聞いたほうがいいと思うよ」と言った。
「うちのおじいさんが、「大愛」は両親の愛より百倍大きく、おじいさんの愛より千倍大きいと言ったんです。それなら先生の愛より何倍大きいのと聞いたら、算数の先生に聞くように言われたの」
「ははぁ、なるほど!」
算数の先生は、昔、おじいさんの生徒だった。だからすぐおじいさんの意図が分かったのだ。
「おじいさんは、昔、わたしの先生だったんだよ。そうすると、わたしはだれに聞いたらいいんだろうね。つまり、「大愛」というものは、そんなに簡単に何倍だとか測れるものじゃないのだと思うよ。答えはその源(みなもと)から探したほうがいい。インゲン豆のほうから探す、ってことかな」
先生が、しごくあっさりと言った。
「みなもと…。インゲン豆…、ですか?」
翔くんが、聞き返す。
(でも、そのみなもとって、どこにあるんだろう?)
算数の先生は、何を思い立ったか、机の引き出しから一冊の古い画集を取り出した。もう表紙もなくなっており、僧侶の似顔絵のようなものがうっすらとみえていた。
「これはね、昔、君のおじいさんから貰(もら)ったものなのだが、翔くんにあげるよ。この中から答えを探してごらん。見つかるといいね」
(大変なもの、もらっちゃった!)
翔くんは、宝物をもらったように古い画集を胸元に押し抱き、先生にお辞儀をするなり、職員室を飛び出して行った。
放課後を、今日は待ちかねた。
校庭の隅の木陰まで走り、翔くんは逸(はや)る気持ちで画集を開いてみた。
そのうちに、ページをめくる翔くんの手が止まった。
恐ろしい絵を見てしまったからだ。
それは、戦争の場面だった。
古代の戦争で、両軍が殺し合っている血腥(ちなまぐさ)い場面だった。
一方の軍旗に、「明」とあった。きっと、おじいさんが言っていた明朝の軍隊だろう。そしてもう一方の軍旗には「清」とあった。
翔くんは、先生が言っていたことを思い出した。「江戸幕府」を勉強したときに、先生は、江戸時代は中国でいえば明と清という王朝が交替するころにあたると話されていたのだ。
でも、「明」と「清」両軍の戦争が、インゲン豆が日本に来た話と何か関係があるのだろうか。
翔くんは、いよいよ興趣(きょうしゅ)をそそられ、夢中で画集のページをめくっていった。
時間が経つのも忘れてしまった。
そしてやがて、翔くんは膝小僧を叩き、声を出した。
「そうか、やっと分かった!」
「ええっ、何が分かったの?」
麗ちゃんが、傍にいた。
「お兄ちゃん、こんなところに隠れて何みているの?」
「インゲン豆が日本に来たわけがわかったんだよ。きっと答えを見つけたぞ!」
麗ちゃんはまるで先生のように後ろ手に組み、お兄ちゃんに質問した。
「ふうん。それじゃ、おじいちゃんが言ってた「大愛」って、結局何倍なの?」
「それはまだだよ。でも、きっと画集の後ろのほうに書いてあるさ」翔くんが頭を掻く。
遠くで、どこかの寺の鐘の音が聞こえた。
第六話
翔くんと麗ちゃんがランドセルを背負い、元気いっぱいで家に帰ってきた。
「おじいちゃん、おじいちゃん!」
家に入るなり、翔くんが大きな声を出す。
「分かったよ。インゲン豆がどうやって日本に来たのか分かったよ。」
でも今度は麗ちゃんが兄に追いつき、息を切らしながら言った。
「まだだよ!お兄ちゃん…まだ分かってないよ。おじいちゃんが言った「大愛」、大愛は何倍かって分かってないよ!」
おじいさんは思わず相好を崩し、孫たちを見て目を細めた。
「急がないで、急がないで。まずは水でも飲んで、ゆっくりお話しよ」
翔くんがおじいさんから渡されたカップを取るなり、一気に飲み干した。
「おじいちゃんすごいよ。算数の先生はおじいちゃんの生徒だったんだね。先生がおじいちゃんに昔もらったっていう画集をぼくにくれたの。自分で探すようにって」
翔くんはそう言って、ランドセルから画集を出し、おじいさんに見せた。
画集はもうかなりの年代物で、あちこちがボロボロだった。何ページか、無くなっているページもあった。
おじいさんはそれを見て、少しの間、昔を思うような目をしていた。
「そこで、何を見つけたんだい?」
麗ちゃんがすかさず横入りし、
「お兄ちゃんはただインゲン豆を見つけただけよ」と言ったのだが、その先は出てこなかった。
翔くんが振り返って、麗ちゃんを睨(にら)んだ。
そしてページのとんでいる画集を指しながら、おじいさんに言った。
「昺ちゃんが有名な隠元禅師様になってから、美味しい四季豆を日本に持ってきたのはわかったの。でも「大愛」が何倍あるのか、それはまだわからないの。ごめんなさい」
「大丈夫、大丈夫。もう大昔のことだし、画集も不完全だ。おじいちゃんが空いてるところを埋めてあげるから」
「でもこれは画集でしょう?どうやって埋めるの?」と、麗ちゃん。
「お話で埋めるんだよ」と、おじいさん。
麗ちゃんはまだ要領を得ないでいる。
「アッタマ悪いなぁ、麗は。おじいちゃんは、物語をお話して聞かせてあげると言ってるんだよ!」
「そういうことね!すてき。お話聴くのは自分で画集を見るよりずっと面白いわ」
「麗ちゃんはね、自分で頭を動かすのが面倒なんだ」と翔くんが眉根を寄せる。「あら、それならお兄ちゃん、インゲン豆のお話してちょうだいよ!」麗ちゃんも反撃だ。
「そうだね。それもいいね」
おじいさんは、この機会に、ちょっぴり翔くんにチャレンジをさせてあげたいと思ったのだ。
「翔くんはもうインゲン豆の由来が分かってるようだから、翔くんに話してもらおうか。」
「いいよ。でもうまくできないとき、おじいちゃん助けてね。」
翔くん、勇気を奮い起こし、ごくりと唾を呑み込んで、頭を上げた。
おじいさんが、身をよじって水の入ったコップを手にした。
麗ちゃんがコップを受け取り、翔くんに手渡した。
翔くん、喉を潤し、語り始める。
「画集にはね、こうあったの。昺ちゃんが梅ちゃんについて黄家の庭に入った。大きな桑の木によじ登って桑の葉をいっぱい取った。頭を上げて遠くを見ると、青々とした畑があったんだ。とても嬉しかったんだと思うよ」
麗ちゃんはお兄ちゃんの見事な語り口にびっくりした。そして思わず聞いた。「なんで?」
おじいさんも、翔くんの天賦の才をひそかに誇りに思った。そこでわざと聞いてみた。
「そうだね、なんでだろうね?」
翔くんは、落ち着きはらって言った。
「それはね、昺ちゃんの家は貧しいから、土地まで痩せていたんだよ。だからきっと、畑もそんなに良く育っていなかったんだよ」
麗ちゃんは急に同情顔になって、しようがないのね、と言った。
「しようがなくなんてないよ!」今度は翔くん、断固として言う。
おじいさんが、二人を見守っている。
「昺ちゃんには方法があったんだ。昺ちゃんは桑の木からスルスルおりて、木の下にいた梅ちゃんに何かささやいたの。梅ちゃんはそれを聞いて、大笑いして、いいよいいよと言ったんだ」
「どうして笑ったの?なにが面白かったの?」
麗ちゃんは待ちきれない。
「昺ちゃんのアイディアがあんまりよかったものだから、梅ちゃんが笑ったわけ?」
翔くんは、語り部の役を楽しみ始めた。
「早く教えてよ!どんなアイディアだったの?」
翔くんは物語の登場人物にでもなったかのように、勿体ぶって、麗ちゃんの耳のそばで何事かささやいた。麗ちゃんの目がきらりと光った。そして言った。
「おじいちゃん、お兄ちゃんがおじいちゃんにテストを…!」
翔くんが急いで妹の口を塞(ふさ)いだ。
「わたしをテストしたいの?」思わずおじいさんが大笑いだ。
「そんなの無理だよね!」と言いながらも、翔くん、ニヤニヤしている。
****** ****** ******
「二人してわたしをテストしてみたいんだね?でも、どんなテストなのかな?」
おじいさんは、わざと心配そうな顔をしてみせた。
麗ちゃんが、いきなり切り出す。
「昺兄ちゃんはどういう方法で梅ちゃんの家のインゲン豆を採ったでしょうか?」
「答えは画集のなかにあったんじゃないのかい?」
「画集には、半分しか載ってなかったの」と翔くん。
「どの半分かな?」
「梅ちゃんから、お兄ちゃんの黄道周に聞いてもらうの。もうすぐ糸を吐くお蚕さんと梅ちゃんの家のインゲン豆の種を交換させてもらうの」
おじいさんが目配せする。
「では、あとの半分は…?」
「万が一黄さんがオーケーしなかったら、お蚕さんを黄さんの机に置いて驚かせるの!」と麗ちゃん。
「麗!全部言っちゃったじゃないか!もう、どうテストするのさ?」
「ははっ、智恵が働くね!でも、画集にはそんな悪巧みは出てこないよ」
おじいさんは大笑いだ。
「お兄ちゃん、悪いよ!わたしを使って、おじいちゃんをテストしようとするなんて!」
「ごめんなさい。インゲン豆を交換する方法なんて、本当は思いつかなかった」と、翔くん。ちょっと、しおらしくなった。
おじいさんが、噛んで含めるように、ゆっくりと話し始めた。
「いいかね。歴史の物語はね、客観的で合理的なのだよ。わざとなにかを練り上げる必要などない。ありのまま、原色が一番いいんだ。昺ちゃんの願いはもっともなものだったし、梅ちゃんのお兄さんの黄道周も同意した。たしかに、お蚕さんとインゲン豆の良種とを交換したんだ」
翔くんに、なにか閃(ひらめ)いたようだ。
「でもそのころ、まだ「インゲン豆」という名ではなくて、「四季豆」と呼ばれていたのでしょう?」
「その通りだ。そしてそれから間もなくして、昺兄ちゃんは家を出て、お父さんを探しに行った。そして偶然海辺で費通師父と出会い、一緒に島に行くことになり、普陀山に登って観音寺に着く。仏門に入っての修行が始まったんだよ」
「修行って、なあに?」
麗ちゃんが首をかしげる。
「今まで経験したこともないことを、コツコツと、忍耐強く学ぶことだよ」
「きっと、とても辛いことだよね?」翔くんと麗ちゃん、異口同音に言う。
おじいさんは、しばらく考えてから言った。
「そうだね。辛いと言えばもちろん辛い。しかし、我慢できなくても耐えるほかないのだよ」
「耐えられないほどの苦しさって、いったいどんなことなんだろう…」
麗ちゃんが溜息まじりに言った。
「男の子だもの。ぼくは。苦労なんて恐れないよ!」翔くんが威勢を張った。
「よく言った。でも水汲みとか薪割りとか、きみにできるかい?」と、おじいさん。
「水は担げないけど、きっと水を汲むことはできるよ。薪割りっていうのは…、見たこともないけど」
「では、床や窓拭きはできるかい?」
「窓拭きなら、わたしもできるよ。でも、床は…大変ね!」麗ちゃんが口を挟(はさ)む。
「仏門に入ればね、できる仕事は当然だけど、できないことも、学びながらやっていかねばならないんだ。疲れない仕事もあるが、疲れることなら、なおさらやらねばならないのだよ」おじいさんが、諭(さと)すように言った。
「そんなに大変なことを、昺ちゃんはどうやって続けていけたの?」
「全て、精神の力で支えていたんだよ」
「精神の力って、そんなに大きいの?」
「ああ、それはそれは大きいよ!空より大きいほどだ!」
兄妹が、話に惹(ひ)き込まれていく様子が伝わってくる。
「一冊の本が、精神の力を解き放ったんだ。費通師父から頂いた一冊の本だよ」
「ええっ、ただの本が?それってどんな本だったの?」
翔くんは、意表を突かれたような声を上げた。
「涅・槃・心・経。仏教の本だ。二百五十六字から成っている」
おじいさんは、一語一句、はっきりと発音した。
麗ちゃんは、聞ければ聞くほど、分からなくなった。
「仏教の本?うち…うちの仏壇にもあるの?」
翔くんは、ありったけの知力を巡らそうとしている。
「二百五十六字しかないのに、その力は天より大きいって…?」
「それが精神の力、なんだよ。多くの人々の心を愛で満たしていく力。労苦にも耐え、不可能を可能に変える。このような力を、いったいどのように量ったら良いものかね」おじいさんの口調が、次第に熱を帯びてきた。
「大きいんだね。本当に、大きいんだね!」麗ちゃんが言った。
翔くんにも、ようやく感じが分かってきたようだ。
「わかったよ、おじいちゃん。昺ちゃんはこの仏典を学んだことで何でもできるようになった。とっても有能になったってこと。そうなんでしょう?」
おじいさんはこのとき、心からの喜びを感じた。
「ふたりとも、賢くなったね。」
「お兄ちゃん、きっともうすぐトランスフォーマーになれるよ!」と麗ちゃんがいたずらっぽい目をして笑った。
「もう言うなよ!いじめるなよ!」翔くんの頬が、すこし赤くなった。
おじいさんが、また大笑いだ。
第七話
中国の東海に浮かぶ「舟山群島」は、まるで星くずが月の周りに集まっているような形をしていて、普陀山の観音寺を、ことさら仙人境のように際立たせている。このあたりで「銭塘江」が大海に注ぎ込んでいるのだが、まるで大蛇が真珠を呑み込んでいるようにもみえる。
朝日が昇ると、霞(かすみ)が立ち上る。
観音寺が朝焼けに映え、この世のものとつかぬほど神秘的だった。
昺が、庫裏(くり)の裏手から出てくる。
肩に空になった水桶を担ぎ、ゆったり、のんびり、愉しげに、水を汲みに行こうとしている。
前方に、畑が見えた。
昺は足を止め、青々としたインゲン豆畑を眺めていたが、その中の一株が外側に倒れそうになっているのを見つけ、桶を置いて直してやった。丁寧に、心を込めて。
石段づくりの参道が、遥かに連なり、望み見れば、向こう側に泉の水面(みなも)がきらめいている。耳を澄ませば、水音が聞こえるほどの静けさだ。
昺は歩調を速め、泉の傍にやってきた。
枡で水を桶に汲んで、そのまま戻ろうとしたが、渇きを覚え、しゃがみ込み、両手で泉の水を掬って一口飲んでみた。
一息入れて、立ち上がろうとしたその時だった。目前の草地で、青蛇が一匹の亀に巻き付いているのを見つけたのだ。
昺は草地に近づき、手を伸ばし、青蛇と亀をゆっくりと離した。片手で青蛇を草地に放り出すと、もう一方の手で、小さな亀をしっかりと手のひらで包んでやった。
陽射しが木立ちを縫い、あたりを柔らかく照らしていた。昺は頭(こうべ)を上げ、亀を懐にしのばせると、水桶を担いで寺に戻った。
普陀山の参道を、一歩、一歩、踏みしめて登る。昺は、ずっしり重い水桶を担ぎながら石段を登り、上って行く。
桶は大層重いはずなのに、軽々と持ち上げているようさえ見える。
修行の成果だった。
費通師父が、水を担いで登ってくる昺の姿をとらえていた。意気軒昂な様子が、いかにも健気にみえた。
昺が近づいてくると、費通は、しばし休憩するよう手振りで伝えた。そして、手ぬぐいを昺に渡した。
昺は恐縮し、あわてて頭を振った。しかし、その顔にはほとんど汗が滲んでいなかった。
「昺よ。鍛錬の成果、見事に出ておるぞ」
費通が、満足げに言った。
「導師のご指導の賜物です。丹田の気を使っております」
「昺よ。おまえは、夜は読経、朝は水汲みで、けっして弛まぬ。文武は一張一弛。よくよく心得ているものとみえる」
費通はやさしく言うと、昺の懐に目をやった。
昺は、すぐさま懐から亀を取り出し、費通に、いましがた見つけた亀と青蛇の故事を話して聞かせた。
「よろしい。善悪をはっきり分け、そして善を積みなさい」
費通は昺を褒(ほ)めた。そして、そう一言言い終わると去っていった。
昺は、水桶を担いで庫裏に入ると、亀を竹かごに入れた。そして、身を翻し、斧とかごを持つと、庫裏の裏手の薪が積んであるところに行き、薪割りをはじめた。手慣れたもので、あっという間に割られた薪が山積みになっていく。
突然、遠くの方から、僧侶たちが武術の稽古をしている「へんっ、はあっ!」という掛け声が聞こえてきた。昺は顔を上げ、籠が薪でいっぱいになったのを確かめると、長めの薪を二本掴み、姿勢を正し、遠来の掛け声に合わせ、自分も練武を始めた。
打てば打つほど、武術の功夫に没入していく。
普陀山の霧が徐々に濃くなり、昺の姿を次第に包み込んでいった。
****** ****** ******
濃霧が晴れ、人影がみえてきた。
昺は、すでに身の丈豊かな若者となっており、修行に励む勇ましい姿が、僧侶たちの方陣の中にあった。
僧侶たちが、高い台座に立った費通師父から訓令を受けている。
「阿弥陀仏、神佑普陀!諸君の目にもすでに明らかなように、昺はまだ剃髪(ていはつ)こそしていないが、一心不乱に読経をし、苦しい修行にも耐え抜き、幾つもの春秋を越し、ひたすら能力を磨いてきた!」
費通はここで手を打ち振り、大音声で宣言した。
「本日、ここで腕比べをおこなう!文武両道を競うが、勝者は決して驕らぬこと。諸君らの未来を輝かせるためにおこなうのだ!林氏曾昺!昺よ、来たれ!」
昺が大きな声で答え、さっと大きく踏み出し、台に飛びのった。
抱拳礼の後、「捏槃心経」の暗誦を始める。
一気に二百五十六字を暗誦した。見事に抑揚の効いた声調だ。一同暫時静まり返ったが、やがて喝采が起こった。
「拙僧、弟子は数百人にも上るが、心経の精髄を能くする者、民間の信徒にあってはこの子だけだ。出家の縁(えにし)あらば、かならず証果(しょうか)を得られんものを!」
費通は、心を打たれていた。
つづいて、さまざまな流派による拳法演武となった。
拳脚健身、内功自保。強と強が連なれば、無辜(むこ)の民を守ることさえできるのだ。
仏の教えは、慈しみを本にして、普陀山の正気、まさに宏大である。
昺はこの「真・善・美」の気風の中で、頬を紅に染め、全身に躍動する力を感じていた。
第八話
普陀山観音寺のそばに、四季豆の畑がある。
時が経ち、昺は、その畑の傍らで、費通と別れる出立の日を迎えていた。
昺は荷物を背負い、手にいつぞやの亀を入れた竹篩を下げていた。
費通は、傍らの畑を指しながら、
「昺よ。おまえは長年の修行により、文武両道でめざましい進歩を遂げた。また、寺のために此処にすばらしい四季豆の畑も作ってくれた。普陀山は、おまえに心から感謝をしている」と語った。
昺は頭を垂れ、去来するさまざまな思いを噛みしめていたが、やがて、
「凡ては恩師である師父のおかげです。今日はここでお暇し、家に戻らねばなりませんが、いつか必ず大恩に報いるよう、きっと精進いたします」と語った。
費通の目に、涙が光った。
そして、昺の後姿を、その姿が見えなくなるまで見送った。
****** ****** ******
昺が普陀山を去ってから、数ヶ月が経とうとしていた。
長旅も終わりに近づき、なつかしい黄檗山道に戻ってきたのだ。
昺はゆったりとした歩幅で歩いていたが、疲れはほとんど感じられなかった。ぶら下げている竹篩がゆらゆらしていて、竹篩にいる亀までのんびりしているように感じられる。
上り下りの、まことにさかんな山道である。
昺は、高台に上がったところでいったん歩みを止め、遠方を望んだ。
故郷(ふるさと)が、其処にあった。
ふと、彼は村口にある石涼亭のほうを見た。
梅の姿が見えたように、思えた。
そうだ!梅に違いない!あれはきっと、梅ちゃんだ!
「梅ちゃん!」
昺は、大声を張り上げ、亀の入った竹篩を高く挙げた。
「昺兄さん!」
梅は、涼亭から転げるように駆けてきた。
昺も、夢中で彼女のところに駆けだした。
竹篩の中で、亀まで喜びで踊り出している。
梅は、息を弾ませて昺の前まで来たが、いざとなると何も言えなかった。
昺は、すらりと美しくなった梅を眩(まぶ)しく感じた。
何かを思い出したように、亀を入れた竹篩を梅に差し出した。
梅は小首をかしげ、竹篩を受け取りはしたが、思いを込めた目は昺の目を見つめたままだ。
昺は、いたたまれぬほど、顔がほてり、熱くなってしまった。
梅は腰をかがめ、竹篩を開けてみた。一匹の小亀だった。梅は亀を地に置いて、這わせてあげた。亀は道に沿いて、涼亭の方向に向かって這っていく。
昺と梅は、互いに顔を見合わせ、ひとしきり笑った。そして、亀についてゆっくりと石涼亭のほうに歩き始めた。
亀は、涼亭の前で止まった。
首を回し、後ろにいる二人を見るようなふうである。
亀の様子を見た二人が、また声をあげて笑った。
そのとき、力強い若者の声が響いた。
「梅よ、なにがそんなに可笑しいのだ!?」
果たして、一隊の家来を引き連れた黄道周だった。
「かわいい亀でしょ?外側は硬くて冷たいけれど、内側は温かいの。まるで兄さんみたいでしょう?」梅が微笑んで言った。
昺が黄道周のもとに走り寄り、深々と礼をした。
黄も、破顔一笑である。
「昺、帰っていたのか!まさに「君子三日会わざれば刮(かつ)目(もく)して見よ」だな!」
梅も、あらためて成長した昺の若武者ぶりを見直して、
「普陀山に行ったと聞いたわ。学問を収めたのね。」と言った。
「学問などというものではありません。そんなことを言われたら恥ずかしくなります。」と昺。
黄道周は、掌に載せた亀を指さし、
「昺、ほら、亀の甲羅の文様、なんだか八卦の形に似てないかい?」と言った。
「確かに。八卦はとても神秘的なものなのですが、そう、もしかすると天意、なのかもしれませんね。」と昺。
「嘘よ、嘘!天意だとか、八卦だとか!」
梅が、天真爛漫な声を出して駆け出していった。
昺と、黄道周が、苦笑しながら娘の後を付いていく。
****** ****** ******
夕刻となった。
夕餉の準備を始めた家々から、煙が幾筋か立ち上っている。
どこかから、鶏や羊の鳴き声も聞こえた。
昺は、思い出の詰まった茅葺の家に辿り着くと、感極まって叫んだ。
「母さーん!」
ほどなく、粗末な戸にすがるように、痩せ、そして年老いた母親が現れた。
母親の目に、喜びの涙があふれ出た。
昺は、荷物を落とし、跪いた。
「母上、わたくしは親不孝者です!父上を探し出せず、こうしておめおめと故郷に戻ったのですから!」
二人の兄も、すぐに出てきた。
涙にくれる母子を抱え、中に入った。
「帰ってくればいいんだ!もうこれでいいんだ!でも、おまえ、こんなに長い間、どこで苦労してきたんだい?」母親が、訊(き)く。
「わたくしは苦労などしてはまいりませんでした。普陀山の観音寺で、新しい生き方を見つけたのです。母上、わたくしには、母上にお願いがあるのです。僧侶になることをお認め頂きたいのです。」
ところが母親は、これを聞くや、厳しい表情となった。
「いまは、認めません。どうしてもと言うのであれば、わたしが死んだ後に剃髪するがよい」
昺は、愕然(がくぜん)とした。
しかし、すぐさま、
「母上、どうかお怒りをお鎮めください。わたくしはかならず孝行の道を第一といたしますから!」
言い終えるや、昺は、少しだけ身を転じ、母親の背中をさすりながら、そっと落涙(らくるい)したのだった。
第九話
陽光を浴びた黄蘗山の緑がざわめいているように見えた。
こんもりと茂った黄蘗の枝から、清々しい香りが漂ってくる。
山腹に拓いた畑で、昺が四季豆の種まきに没頭している。
ややあって、彼は腰を伸ばし、辺りの空気を胸いっぱい吸い込んだ。
向こうから、黄府の家来がやってくるのが見えた。
昺はその家来の顔に見覚えがあった。石涼亭で黄道周と再会した折に出会ったことがあった。
男は、藤で編んだカゴを抱えており、昺の前に来ると、微笑みながら、
「お邪魔いたします。これは、わが主人から託された飯であります」と言った。
昺は大股で道に飛び上がり、丁寧に礼を言い、黄府の家来が両手で捧げている藤箱を受け取った。
開けてみると、そこにはあざやかな、収穫したばかりの四季豆が入っていた。
「わたくしはまだ種まきをしているというのに、黄府ではもう収穫ですか!」
昺が、快活に言った。
「はい、仰せの通りで。まことに「四季豆」と呼ばれる所以(ゆえん)であります」
家来はこう応えた、やや真面目な面持ちとなり、
「主人によれば、今宵(こよい)は星空がよく見えそうなので、昺様をお招きし、ともに天象を観たい、と申しております」と言った。
「ご厚意、ありがたく存じます」昺が謝意を述べた。
「くれぐれもご遠慮なく、とのことでした。わが主人も殊(こと)の外(ほか)楽しみにしておりますゆえ」こう言って、家来は去っていった。
****** ****** ******
夜になった。
空は、満点の星空だった。
黄府の庭にある桑の木の下で、黄道周と昺が、書斎の外にある石造りの腰掛けに並んで座り、星空を仰ぎ見ている。
黄道周は、詩を作ってみたいと思った。
「夜空は、もともと無色なのだが、星海の美しさをこうして賞(め)でることができる。昺よ、不思議だとは思わぬか?」
「兄上のお気持ちゆえ、なのでしょう。今宵は、星海だけでなく、何事も美しく見えるではありませんか」
「その通りじゃ。しかし昺よ、そなたには、この無辺の天空が、畢竟(ひっきょう)どれほど大きいと思われるか?」
「それは、それを思う心がどれほど大きいのか、に因るのでありましょう。」
昺が、静かに答えた。
黄道周が、思わず振り返った。
「昺よ、眼を開かれる思いじゃ!そちは将来、かならず一(ひと)廉(かど)の人物になるであろう!まことの兄弟に、なってはくれぬか?」
「兄上、果てない天空の下、もともと本来「一家」ではありませんか!」
昺は、穏やかにそう言うのであった。
実はこの時、二人の後ろで、書斎にいた梅が彼らの話を聞いていたのだった。梅は、喜びを隠しきれないといった様子で、密かに笑った。傍らにいた家来が、彼女に、いい加減に盗み聞きはやめるよう、あきれた様子で手を振った。
やがて梅は、抜き足差し足をしながら、家来とともに、そこを離れた。
蕾(つぼみ)が開き、花が落ち、流水が東に逝った。
昺の母親が、命を引き取った。
喪に付す兄弟三人が、隊列の前をゆっくりと進んでいく。紙銭が舞い、そして、道行く人々の足元に落ちた。
****** ****** ******
萬福寺に向かう石段造りの参道を、昺が、力強く、一歩一歩を踏みしめるようにして上っていく。
この時代、萬福寺はすでに高名な寺であった。
殊に、費通が仏教の聖地である普陀山よりここに移り、萬福寺の住持として就任してからというもの、線香が絶えることはなく、法事も多く、ますますその名を高めていた。
昺は、そうした便りをかなり前に聞いていたのだが、母親との約束を守るため、これまで孝行(こうこう)専一(せんいつ)で尽くしてきた。しかし今日、晴れて自らの願いにより、師の元に戻ってきたのであった。
師が当年、普陀山にいた時に教えた「善悪をはっきりと分け、善行を行え」という教誨(きょうかい)を、昺はずっと胸に刻み、これまでの年月を過ごしてきた。今日は、当年師と別れた時に持っていた亀の入った竹篩を持ってきたが、竹篩の大きさが、亀の成長と、自らの心の成長を表しているようにも感じていた。
威容を示す大雄宝殿で、高僧の装いをしている費通には、威厳が漂っていた。昺が寺に着いたとき、費通は端座(たんざ)しており、仏珠を手に、唇を動かしていた。
「師父!」
昺は、仏殿に入るなり、跪いた。そして、嗚咽しそうになるのをようやく堪えながら、
「師父、昺は、お会いしとうございました!」と声を振り絞った。
竹篩が、乾いた音をさせ、床に落ちた。
費通も、全身を震わせ、立ち上がった。
小走りで、昺の元に向かう。
そして昺の腕を取りながら、涙を堪え、「昺よ、わたしもそなたに会いたかった。仏に向かい、そなたの無事を祈り続けておったぞ!」と語りかけた。
昺には、仏殿の中心にお座りになった釈迦像が彼に微笑みかけているような気がした。
ダーン!ダン!ダン!
時を告げる鍾の音が響いた。偶然なのか、はたまたなにかの啓示であったのか。昺は、久しく、確信に満ちた喜びの中にいた。
竹篩に入っていた亀も、鍾の音で頭を伸ばした。
****** ****** ******
物語を語ってきたおじいさんは、翔くんと麗ちゃんが、目を見開いて話に没頭している様子に気づいた。二人はまるで、昺の生きる世界に入ってしまったかのようだった。
おじいさんは、急いで言った。
「びっくりさせてしまったかな?昺ちゃんは二十八歳になってから、やっとのことで、お坊さんになったんだものね。本当に大変だよね!」
第十話
おじいさんの「インゲン豆物語」は、昺ちゃんが二十八歳のときに出家し、正式に萬福寺の費通住持を師とするところまできた。
傍らで一心不乱に聞き入っていた翔くんがため息をつき、言った。
「昺ちゃんはもうとっくの昔に普陀山に着いていたのに、出家したのはこんなにおそかったんだね…」
おじいさんが指を折りながら、答える。
「それはね、第一は昺ちゃんがとてもお母さん思いの孝行息子だったから、だろうね。お母さんに約束したことはどんなことがあっても守る。だからお母さんが亡くなるまでは決して家を出なかった。第二は昺ちゃんが師父をとても信頼していたということだと思うな。つまり費通師父がどこに行かれようと、必ず探し出せると信じていたんだよ」
麗ちゃんが、ちょっと待ちきれないでいる。
「おじいちゃん、だったら、第三は?」
おじいさんには、麗ちゃんの考えていることがすぐに分かった。
「麗ちゃん、梅ちゃんのことだね?」
「そうよ!どうしてわかったの?」
おじいさんが、すこし厳しい顔つきになった。
「梅ちゃんはね、昺ちゃんと、ほんとうに仲の良い幼馴染だ。小さい時から気が合っていたし、大人になってからはなおさら別れがたかったことだろうね。しかし、一心に和尚さんになりたかった昺ちゃんだから、どうしてもわきまえねばならない分別というものがある。男女の別、だよ」
「それって、どういうことなの?」麗ちゃんが口を尖らす。
「どういうことでもないよ。大人の事で、ぼくたちにはわからないことさ」と翔くん。
「そんなのじゃわからないわ!学校の先生だって、わからなければ聞きなさいと言ってるよ!」
「先生が言われてなかったかい?昔、封建社会では女の人に地位がなく、自由もなかったって」おじいさんが、いつもの笑顔で言った。
孫たちは、今度は何も言わずに頷いた。
おじいさんは一口茶を含むと、物語の先を続けた。
****** ****** ******
黄府が、提灯と赤色で彩られている。お祝いの楽の音が、高らかに奏でられている。
嫁入りを待つ黄幽梅は部屋に引きこもり、暗然と涙を流し、なかなか着替えようとしない。兄の黄道周が部屋の近くを行ったりきたりしながら、妹の出てくるのを辛抱強く待っている。
銅鑼や太鼓が打ち鳴らされる中、爆竹がいっせいに音を立ててはじけた。
黄府からようやく嫁入りの駕籠が担ぎ出され、行列がゆっくり動き始めた。
駕籠が萬福寺の近くまで来たとき、御簾(みす)の隅がめくられ、梅の悲しげな瞳が現れた。その目は万感の思いを湛え、寺院のほうを遥かに見やっている。
駕籠はやがて、曲がりくねった山道の奥へと分け入っていった。
ちょうどそのころ、萬福寺では昺の出家の儀式が執り行われようとしていた。
費通が長老の装束を身に纏い、昺に向かい、厳かに語り出した。
「苦海は果てしもないが、振り返ればそこは彼岸である。この世の体「林曽昺」はここに去り、法名「隠元隆琦」が生まれた。黄檗の宗を継いで、萬福の泉を沸き立たせ、衆生を済度せん。さすればその名、とこしえに語り継がれることであろう!」
寺を取り囲んだ郷里の人々が、その様子を見て、感嘆の声を上げた。
「阿昞(昺の幼名)は普陀山から帰ったとき、すでに出家を望んでいたのが、老いた病身の母親の世話のため、長年忍耐してきたのだ。なんと親孝行な青年であろうか!」だれともなく、声が上がった。
また、
「昺は黄府の令嬢と慕い合っていたのだが、いかんせん身分違いだから、今日こうして出家するのもお互いにとって良いことだろうよ!」
そんなことを言う口さがない者もいた。
****** ****** ******
「ほんとうに、昺ちゃんってやさしく、親孝行だったんだね…。」
翔くんが、独り言をもらした。
だが、麗ちゃんは相変わらず少し不満気だ。
「それじゃあ梅ちゃんは?あんまりだわ。かわいそうよ!」
おじいさんは、黙って聞いている。
孫たちの、歴史上の人物に対する細やかな思いやり、思い入れがとてもうれしかったのだ。
第十一話
庭に陽射しが溢れていた。
おじいさんが孫たちと共に石卓を囲み、卓上には摘まれたばかりのインゲン豆。三人で豆の角を取っていたのだが、おじいさんはいつしか豆を持つ手を休めて、なにか物思いにふけり始めた。
翔くんと麗ちゃんはおじいさんのおかしな様子を見ていたが、つい「くくっ」と笑い声を出してしまった。
おじいさんが、その声で我に返った。
「このインゲン豆を見ていたらね、昺ちゃんが和尚さんになったばかりのころ、費通師父に言われて、外地に修行に出たという故事を思い出したのだよ。彼はね、インゲン豆の種を持って修行にでるや、四季をかまわず、道すがらこれを播いたそうだ。つまり、お百姓さんたちに因果応報の仏教思想を伝えながら、おいしい豆もプレゼントしたんだよ」
「そういうことだったの!道理で「四季豆」が「インゲン豆」に変わったのね!」
と麗ちゃん。
「へえ、じゃあ、修行ってどういうことなの?」今度は翔くんだ。
「いい質問だね。そうだな。簡単に言えば、修行とは和尚さんの勉強、のようなものだよ。苦労に耐え、性根(しょうね)を鍛え、身を以て範を示し、正気を遍く伝えん、といったところだな。」
「なんだかおじいちゃん、校長先生みたい」と麗ちゃん。
「和尚さんには修行があって、僕らには宿題あり、です!」と翔くん。
「はい、よくできました!そうしてこそ、世の中が発展していけるのだよ。」
世の中、といえば…。
そう。おじいさんの物語も、いよいよ明末清初、戦乱の世に差し掛かってきたのであった。
****** ****** ******
朝靄たちこめる中国北方の大地。静寂に包まれている。
万里の長城「喜峰口」の堅固な関所が微かに見える。
濃霧の中、次第に近づく地響きのような馬蹄。近づくに連れ勢いを増し、進軍の太鼓の響きのようですらある。
霧の中に旗のようなものが見えた。
それが、次第にはっきりとしてくる。
軍旗に大書された「清」の文字。旗が折からの風にはためく。
怒涛の勢いで関所に押し寄せた清の鉄甲騎馬軍団。もはやその勢いを押さえられるものはいない。
喜峰口の関は、しっかりと閉ざされている。
城壁の上には明の軍隊が一分の隙もなく待ち構えている。
「明」の大旗の下には、大将である朱虎が剣を構えて仁王立ちする姿があった。
清軍は弓矢の射程距離にまで迫ると、一文字に並び、長蛇の陣を組んだ。
そして一人の将校が弓を執り、城門のやぐらめがけて挑戦状を射込んだ。
朱虎は矢から挑戦状をもぎ取って開き、一読すると顔色を変えて激怒した。
そこにはこう書かれていたのだ。
「朱虎よ、朱虎、ねずみのような臆病者!門を閉じたその外は、いったいだれの領土なのか?」
朱虎の吼えるような一声で、出撃が命ぜられた。
喜峰口の門が大きく開かれ、朱虎が真っ白な軍馬にまたがって飛び出し、五つの隊伍に編成された将兵を従え、精鋭の勇を大いに発揮して清の大軍に攻め込んだ。それはあたかも虎が狼の群れに飛びかかり、分散させて包囲し殲滅する勢いだった。
蹄の音が次第にまばらになり、鬨(とき)の声が天地を圧した。
両軍入り乱れての白兵戦。刀剣が火花を散らせてぶつかり合い、軍服が血に染まる。すさまじい惨状が目前に広がっていった。
戦火は激しくなるばかりで、あちらこちらに煙が立ち上り、殺し合いの雄叫びが大地を震わしている。
清軍はこのときすでに戦略を変更し、指令旗を高々と掲げていた。
明軍は清軍を各個部隊に分裂させ、包囲殲滅する戦法を採っていた。しかし、朱虎が逆に包囲される展開となり、明軍は次第に隊列を乱され、朱虎も、右往左往するばかりとなり、局面の変化に対応しきれず、疲弊を募らせていった。
清軍は一方で出撃した朱虎を牽制し、一方では城内への猛攻撃を行い、無数の勇士が雲(うん)梯(てい)を使って城壁をよじ登った。
城壁上では、迎え撃つ明軍のほうが多勢に無勢の戦いを強いられ、大半が死傷しつつあった。
そのうち、城壁に上った清軍兵士が勢いに任せて軍旗を振ると、明の兵士たちはそれを見て戦意を喪失し、次々に敗走していった。
朱虎は取り囲まれ、またがっていた白馬も鼻息を荒くして堂々巡りを繰り返す有様となった。朱虎は剣を揮(ふる)い、大声で叫び声を上げると、馬を御して跳び上がり、包囲を突破せんと最後の賭けに出た。
土煙の中、主人も、白馬も、煙のように見えなくなった。
喜峰口が陥落すると、清の騎馬軍団を遮(さえぎ)るものはなにもなかった。
清軍は荒々しく南下を続け、これにつれ、沿道の難民の数が膨らんだ。
家や田畑を追われた幾多の難民が列を成し、老人や子供を連れ艱難にあえぎながら進んでいく。
嘆きの声、怨嗟(えんさ)の声が、どこまでも続いていた。
朱虎を乗せた白馬は、山奥の鬱蒼とした木立に守られた前で止まった。
ひんやりとした月明かりに照らされ、金箔で記された「大仏寺」という横額がぼんやりと見えた。
朱虎は傷つき、疲労困憊した身体を馬から降ろし、剣を杖のように使いながら、ゆっくりと寺の門をくぐった。
清軍の騎馬軍団は一路南へ、破竹の勢いで進軍していく。
明の城市はあちらこちらで破壊され、血の海と化し、人も馬も、地に倒れた。
死体の山の中から、夜陰に紛れ、一人の明の将軍が這い出して来た。
彼は清の哨兵を襲い、鞭を振るうと、南明の都へと馬を走らせた…。
ちょうどそのころ。
長江南岸、南明の都。
南明の君主が連日連夜家臣を集め、敵に抵抗する策を練っていたが、文官たちは憂鬱な表情を浮かべるばかり。武官たちも怖気づいていた。
ただ一人、鄭成功大将軍のみが雄々しさを失わず、大きく前に踏み出して、
「揚州を守らなければ退路はない。昔から長江の北に拠点を置いてこそ、長江を天然の堀とすることができるという。いまこそ背水の陣を敷き、決死の覚悟で南下する敵を迎え討つ時である」と主張した。
傍らの黄道周軍師にも胸算用があるようで、鄭成功に賛同し、
「成功将軍の言うとおりだ!進撃しないのは退却に等しいが、いまや退路も断たれている。ならば進撃して天下を成すのみ。聖賢たるわれらが君主は向かうところ敵なし。いまこそ気概奮い起こし、逆境において勝利を得ん」と気勢を上げた。
南明の君主は二人の言葉に力を得、いま一度奮い立って命令を発した。
「鄭成功大将軍は先ごろも台湾を回復し、その功績顕著なり!いまは清を退けるが急務。急ぎ軍を整え、南明を護るのだ!」
すでに空も白み、江南の運河がきらきらと輝いてみえる。
鄭成功は黄道周と共に馬を駆り、運河に沿って東南の大地をめがけ、遠く走り去っていった。
第十二話
南明の都よりさらに南に位置する福建省。
風光明美で、小鳥のさえずりと花の香に包まれる土地柄である。
明清交代期、乱世の戦火も、未だこの土地の平和と静けさを破るところまではいっていない。
此処は、福建省福清の黄檗山麓である。
森閑とした木立の間から壮大な寺院「萬福寺」が、霞が煙る中、厳かな光を放っている。
寺院の裏には整然とした石段が、ひっそり奥深い山道に連なっている。
曲がりくねった山道を少し行くと滝があり、真下に落ちる銀色の水が、しぶきを上げている。
その水しぶきの中、三人の若い僧侶、大眉性善、独立性易、木庵性瑫が肌脱ぎになって合掌している。
かれらは滝つぼの中、一本足で体を支え、もう一方の足を曲げてその膝に置き、まるで鶴のような姿で、頭から滝に打たれ続けていた。
滝の傍らの奇妙な形をした岩石の間を縫って、六十を少し超えたぐらいの禅師が竹の禅杖を手に、ゆっくりと歩いてきた。
その禅杖はまっすぐで、棍棒の様に頑丈だ。老禅師がそれで地を突くと、木魚を打つかのような音がこだました。
隠元隆琦禅師であった。
隠元は滝の前の平らかな草地に着くと、軽やかに飛び上がり、禅杖を振るい始めた。滝の中で石像のように動かない三人の弟子の姿と、草地で軽やかに舞う隠元。「静」と「動」があくまで対照的に、しかもすこぶる調和していた。
突然、隠元が振るう禅杖が降りかかってきた水玉を斬ると、水玉が瞬時飛散し、朝の光が煌(きらめ)いた。
隠元が禅杖をまっすぐに立て、地面を数回打って音を出した。
すると滝の中の弟子たちはその音を聞いて修行を終え、滝から飛び出してきて、隠元の前に並んで立つと、声をそろえて挨拶した。
「師父様、おはようございます!」
隠元は禅杖で地面を打ち、「大眉性善!」と呼ばわった。
「在(ここに)!」と、大眉が大きなよく通る声で応答する。
「今朝のお勤めは如何であった?」
隠元は、穏やかな中にも鋭い眼光を宿す目で辺りを見回す。
「師父様、後ろの山をご覧ください!」
大眉が言い終わらないうちに、隠元は後ろの崖に刻まれた一丈四方の「金剛経」という文字を見ていた。数十名の僧侶たちが崖に捕まって経文を刻んでいる。文字の間で動く人影が見え、石に打ち込む鎚の音までかすかに響いてくる。
隠元は向き直り、頷いて満足の意を表し、すぐまた禅杖で地を打った。
「独立性易!」
「在!」と応えた独立が瞳をくるりとめぐらせ、振り向きざま口笛を吹き、腕を上げて空中で円を描いて合図すると、たちまち山のほうから数十名の僧侶が駆けつけてきた。それぞれ竹(たけ)籠(かご)を背負い、籠は薬草でいっぱいであった。
独立は先頭の僧侶から一冊の書物を受け取ると、隠元に、
「お勤めとして、「本草綱目」に記された薬草のほとんどを採集しました。どうかお目通しを!」と言った。
隠元は次に、がっしりとした体格の弟子木庵がうなだれているのを見て、厳しい声で、「木庵性瑫!」とその名を呼んだ。
「在!」木庵も胸を張って顔を上げたが、その口を突いて出たのは、
「わたくしめ、お勤めに成果なく、まことにお恥ずかしゅうございます!」という慙愧(ざんき)の言葉だった。大きな体に似合わぬ物言いで、このとき木庵の姿が二回りほど縮こまってみえた。
隠元は微笑をたたえ、
「何も恥じることなどない。見なさい、あの者たちの中にはあなたが鍛え上げた立派な片腕たちが沢山いるではないか?」
薬草を採ってきた数名の僧侶が、それを聞いて勇気を得たのか、お互いに目配せしながら少しずつ木庵の傍に寄ってきたので、木庵は恥ずかしそうに照れ笑いをした。
明るい笑い声が緑山に響いた。
弟子たちは隠元に従い、その禅杖の地を打つ音に歩調を合わせて、渓流を飛び越え石を跨ぎ、飛んだり跳ねたりしながら寺に帰っていくのだった。
****** ****** ******
萬福寺の裏庭。
隠元は部屋に入ると禅杖を置き、机に向かって大きな画仙紙を広げ、筆を執り、たっぷりと墨を含ませた。
「人の初め、性本より善」という言葉を発するや、筆を下した。
このとき、瞬間、目前に三人の弟子が滝の中にいる情景が浮かび、筆を、滝がまっすぐ落ちるように画仙紙の一番下まで、一気に書き下ろしたのだった。
濃い墨で書いた一筆が、紙面のほとんど右半分を占めた。
隠元は筆を手に一時沈思黙考し、まさに再び筆を下ろそうとしたとき、寺院の梵鐘が鳴った。すでに午前の講話の時間になっていた。
隠元は未練が無くもなかったが、静かに筆を擱(お)いた。
第十三話
萬福寺大雄宝殿。
僧侶たちが階級別に、ある者は座し、ある者は立ち、静かに隠元を待っている。
宝殿の外の石段や欄干の両側にも大勢の信徒が所狭しと詰めかけており、固唾をのんで導師の来臨を待っていた。
隠元がゆっくりとした足取りで宝殿に入り、釈迦牟尼の像の前に座禅を組んで座ると、宝殿の中でも外でも一斉に「南無阿弥陀仏」が唱和され、その余韻がこだまとなって梁を伝わり、あたりに響き渡った。
そのころ、黄檗山の参道を前後に並び、駆けて来る者たちがいた。
前を行くのは中国と日本を行き来する商船「福州号」の船主何素如、後に続くのは日本の長崎にある東明山「興福寺」からの使者であった。
二人とも、汗だくになって山道を急ぐ。
遠くで梵鐘が鳴るのを聞くや、いよいよ足を速めるのだった。
****** ****** ******
大雄宝殿で仏法を説いていた隠元だが、外の慌ただしい様子を知り、それが何素如らであると分かると、すぐに手を挙げ、殿内に招じ入れた。
ほどなく。
隠元の居室。主と客が座して向き合っている。
机の上に、以前届き、すでに開封してある三通の書簡が並べられている。落款には「日本国長崎興福寺住持逸然性融」という見事な楷書がしたためられていた。
隠元は使者が携えたもう一通の書簡を受け取るや、感慨を込め、
「お二人とも労苦をいとわず、よくもご足労くださいました。」とねぎらった。
すると何素如は片手の拳をもう一方の手で覆う型の礼をして、
「恐れ入ります。どうか書簡の内容をお確かめくださいますように。」と答えた。
隠元は頷(うなづ)き、封を切って書簡を読み出したが、やがて、
「なんと!わが弟子也懶よ!このわたしに思慮が足りなかった故であろう、そなたをわたしの代わりに日本へ遣ってしまったが――不幸にも、遭難したとは!ああ、悲しい哉!ここ数日夜も眠れず、時に訃報を夢にまで見たのはこのせいであったのか!」
ようやく声を絞り出すと、隠元は、はげしく嘆いた。
数ヶ月前のことであった。
隠元は、机の上に置かれた三通の招聘状を手に取り、三通目の書面を手に取り、思いあぐねた挙句、自分の代わりに弟子である也懶性圭を遣わし、仏法を伝えさせようと決めたのであった。
也懶性圭の袈裟からは、海の匂いがした。
也懶の乗り込んだ船が日本へ渡航中嵐(あらし)に遭い、不幸にも大海原の藻屑(もくず)となってしまったからである。だが、也懶の魂は消えず、青い雲となり、黄檗山に漂い着き、隠元の夢に現れ、涙を流しつつ、彼に袈裟を返そうとするのだった。
隠元は夢から覚めたように、突然現実に引き戻された。
そして、日本からの使者が恭(うやうや)しく差し出した也懶の遺品―それがまさに袈裟であった―を受け取った。
隠元はその両目に涙を溢れさせ、決然とした口調で言った。
「弟子が遭難したのは、師匠のわたしのせいである。ここは、親が子の責任を果たさねば、天がお許しにならないだろう!」
彼はそう言うなり、傍らに置いてあった一筆の、「人」とのみ記された未完の書に向かい、その一筆の左側上に「孤旌」という二文字を記したのだった。
隠元の決意を眼前で見た日本からの使者と同行した船主は、感激して跪(ひざまず)き、声をそろえて礼を述べた。
梵鐘が鳴り、夜が明けた。
隠元の部屋の蝋燭はとっくに消えていた。
一晩じゅう眠らなかった隠元は、軽く目をこすり、やっとの思いで、追憶から現実に立ち戻り、元気を奮い起こして大雄宝殿に入ったのだった。
****** ****** ******
壮大な宝殿には、夥しい数の人々がいた。
彼らはそれぞれに尋常ならざる面持ちであったが、それでも秩序正しく、点呼に従い、列を作っていた。
隠元を頭とする日本行きの僧侶と信徒、工匠らは合わせて三十余名だった。
滝に打たれてなお微動だにしなかったあの三人の弟子、すなわち思慮深く智謀に長けた大眉性善、医術に秀でた独立性易、力持ちで忠誠心の強い木庵性瑫等も一行に加わっていた。
信徒の中に、仏像彫刻の名匠であった范道生もいる。大小の彫刻刀を背負ったその姿がひときわ目立つ。
福州号の船主何素如と、長崎の興福寺からの使者も共に帰国の途に加わることであろう。
隠元がこれらの人々を率いて大雄宝殿を出ようとすると、思いがけないことに、外には大勢の僧侶や信徒千人以上が参集しており、隠元に向かい跪いていたのだった。
人々は隠元が出て来ると、にわかに、天地を揺るがすほどの叫び声を上げた。
隠元はいたく驚き、あわてて手を振って制止した。
泣き声が弱まると、隠元は傍にいた後任の住職に「これはどうしたことか?」と尋ねた。すると、
「皆、禅師の日本行きをお引止めしたいと集まってきたのです!」という答えであった。
「皆の衆、どうか悲しまないでほしい!このたびの渡日は三年の約束で参るのである。黄檗の仏法を広め、萬福寺の栄光を顕すために!」
隠元は大きな声でこう宣言し、続けて二句の詩文を詠んだ。
しばし故郷の十二の峰々を離れん。
青空広がり雲消ゆる時(明の復興を指す)再び帰り来たらんと。
後任の住職も進み出て、人々に向かって大声で呼びかけ慰める。
「隠元禅師は日本に渡り仏法を伝えられるが、これは祖先の栄誉を高めるお仕事である。しかも三年でお帰りになると約束しておられる。皆の衆、どうか安心されよ!」
萬福寺の門前で、すでに隠居していた高齢の費通が、餞別(せんべつ)として木箱をひとつ隠元に手渡した。隠元はうやうやしく礼を述べ、これを拝領した。
費通は、木箱を指さし、笑顔で言った。
「餞(はなむけ)をあててごらん。」
隠元は、ややも黙考したのち、恩師の意は深く、大海の如く測りがたし、と答えた。
「では、開けてみなさい。」費通が、おだやかに言った。
隠元は、箱を開け、ひとしきり驚いた。
「恩師のお励まし、痛み入ります!」
木箱の中にあったのは、百粒ほどの、光沢を放つ四季豆の種だったのだ。
隠元が、その木箱を青空に向け、高く捧げ持った。
「四季豆の種!いまや隠元豆の種!」
誰ともなく、そういう声が上がった。
「四季豆四方! 隠元豆永代!(四季豆四方に、インゲン豆は永久に!)」
すると今度は、皆が唱和した。
集まった千人もの人々が、高らかに喜びの声をあげ、その声が山を震わした。
第十四話
日本伝道に旅立つ三十余人は、やがて山道から海辺に通じる大路に踏み出した。僧侶たちが大小の荷物を肩に担いだり車で推したりして運んでいる。十数個の大小の行李には「種」「薬」「書」「芸」などの文字が記されていた。
弟子の木庵が亀の入った籠を持って追いかけてきて、隠元と笑顔を交わす。
道中、ある日のことであった。
後方で馬蹄の音がして、土煙が立った。見れば、うしろから鄭成功と黄道周が率いる一隊であった。
彼らはほどなく僧たちを追い越し、列の先頭まで来た。
隠元を見出すや、すぐさま手綱を引いて下馬し、拱手(きょうしゅ)の礼をする。
「隠元禅師殿はどちらまでいらっしゃるのですか?」鄭成功がまず問うた。
「日本へ渡って仏法を広めます。鄭将軍の管轄地を通らせていただければ、ご恩は一生忘れません」と隠元。
「なんの。仏法伝道にご協力できるのであれば、喜んでお引き受けいたしましょう。最近わたくしが防衛を司っている港に丁度一艘船が停泊しています。隠元禅師殿の渡航にお使いください!必ずご無事にお送りいたしますゆえ」
鄭成功は満面の笑みをたたえ、そう言った。
隠元、これを聞いていたく喜び、合掌して感謝を述べる。
「将軍のご好意、感謝に堪えません!拙僧、将軍のご母堂が九州に居られると聞いております。何かお届けするものなどあれば、どうか何なりとおっしゃってください」
「家書万金に抵(あた)う、とはまさにこのこと。まことに有難き幸せ。お別れのときにきっと禅師殿にお託し申し上げます!」
鄭成功も感激して、こう応じたのであった。
さて、ほどなくして、一行は黄府に到着した。
隠元にとっては、これこそ生まれ故郷である。
黄道周が一行に、屋敷に寄って休むよう熱心に説いた。
****** ****** ******
あらゆる思い出の詰まった故郷。
隠元は、目を挙げて、黄府の大きな桑の木を見つけると、思わず歩調を緩めた。それから回廊に至った時、である。
隠元は其処からそれほど離れていない亭(あずまや)に白髪交じりの婦人が腰掛けているのを見て、慌てて立ち止まった。黄幽梅であった。
幽梅もまた、すぐ隠元を見出した。
二人は見つめ合い、何か言葉を交わしたいと思ったが、ただの一言も出ない。そのうち、隠元が前に進み出て、
「よきかな、よきかな、相見る時難く別れるも亦(また)難し!(相見時難别亦難)」と詠んだ。
幽梅がわずかに顔を上げ、目をそらし、
「東風力無く百花残(くず)る(東風無力百花残)」と続けた。
隠元はこれを聞き、目を伏せて後ろに下がり、元居た場所に戻った。
黄道周は後ろから追いかけて来たが、このありさまを見て、
「わが妹は嫁ぎ先で不幸な目に遭い、もう長年後家(ごけ)を通しているのです。失礼がありますれば、何卒お赦しください。」と言った。
いつの間にか後にきていた鄭成功が、言葉に二重の意味をこめ、
「山河は移せないが、性格は変えられる。惜しむらくは、縁ならん。縁が有るも無いも天の思し召し。なれば、天には情けがないのであろうか?」と言った。
「天に情けがあるならば、わたくしたち僧侶は何のために存在するのでしょう?阿弥陀仏!」
隠元は、静かに手を合わせた。
すると、これまで傍らで目を伏せて黙っていた黄幽梅が、突然問いかけた。
「阿弥陀仏、男女に区別があるのでしょうか?」
幽梅は、隠元が答えようとして、口をつぐむのを見ると、その場を立ち去ってしまった。
後ろのほうで、男たちの笑い声が聞こえた。
第十五話
物語がここまでくると、麗ちゃんの我慢の限界がきた。
「ほら、わたしの言った通りでしょ?梅ちゃんが可哀そうなのよ。おじいちゃん、そうでしょ?」
「うん、そうだなあ…」
おじいさんが少し考え込むような素振りをみせる。
「でもね、梅ちゃんよりもっと可哀そうな女の人だっているよ」
「えっ、梅ちゃんより可哀そうって!どんなふうに?」
麗ちゃんがますます落ち着かなくなってきた。
「どういうふうに、か。そうだね…、たとえば、もう死ぬしかない、何の希望もない」みたいなのかな。
「ええっ?」
今度は、翔くんもいっしょに飛び上がった。
「話せば長くなるよ。さっき、北方での戦争の話をしたよね?明と清が交代したんだったね。だから、北京はもう大清国の首都であるわけさ。都には大清皇帝が住む紫禁城という皇宮が建てられていたんだが、皇宮の中は、皇帝を除けば皇帝の母御である太后、それからたくさんのお姫様たち、数えきれないくらい大勢の女性たちがいたんだ」
「そんなにたくさんだったのかぁ。でもその人たち、みんな可哀そうだったの?」と麗ちゃん。
「みんな権力を持っていたんでしょ?可哀そうなんてことなかったでしょ?」と翔くんも続ける。
おじいさんがここで頭を振った。
「彼女たちの中では、太后だけ、全部何でも決めることができたんだ。いちばん可哀そうな女の人は、その太后に言うことを聞かない人だと思われてしまった人、つまり、太后の気に入らなかった人だろうね!」
「それって、だれなの?」
麗ちゃん、翔くんが異口同音でたずねた。
「董鄂妃。大清国の青年君主、順治皇帝がもっとも寵愛した王妃だよ」
おじいさんが答えた。
「じゃあ、太后が気に入らなかったら、皇帝でもだめなの?」
翔くんには納得がいかない。
「皇帝でも大事なこと決められなかったの?」麗ちゃんも同じだ。
「年若い皇帝だからね。国家の基(もとい)を打ち立てたのはずっと前の世代だ。だから、彼もまた太后が手配する通りに動くしかなかったのだよ。そして、さらに重大だったのは、このことが南明のお寺、隠元禅師にまで関係していたということだね。太后の怒りを買ってしまえば、清軍が南下するときに刺客を送ることもできた。隠元の命をつけ狙う刺客だよ!」
****** ****** ******
紫禁城、清朝皇宮の裏庭。
十八歳の順治皇帝が董鄂妃と水遊びをしている
董鄂妃は皇帝の寵愛を一身に受ける身。何の気兼ねもなく、ひたすら水をかけ合いながら皇帝を追いかける。
二人は幸せの絶頂にあり、陽気な笑い声が絶えることがなかった。
そんなある日。
いつものように嬌声(きょうせい)が響き渡り、ちょうどそこで本を読んでいた孝荘文皇后を驚かせた。孝荘文皇后が目を怒らせ、周りを見回す。
順治皇帝は息を切らせて亭に飛び込むや、孝荘文皇后とぶつかってしまった。
孝荘文皇后はあからさまな不快の色を表し、
「帝におかせられましては如何なさいましたか?」と問うた。
皇帝は息を切らせ、腰をかがめて笑いながら、
「追っ手が迫っています、母上どうか助けてください!」と答えると、孝荘文皇后は怒りを抑えきれず、
「いずこのうつけ者が帝を追いかけているのですか?」と表情をこわばらせた。
順治は笑いながら、
「母上、母上様、怒らないでください。後ろから董鄂妃が…董鄂妃ったら可愛くって!」といよいよ相好を崩すのだった。
孝荘文皇后は、すぐさま怒りを追いかけて来た董鄂妃に向けた。
彼女はひとしきり董鄂妃を叱責(しっせき)し、
「天も法もわきまえず、礼儀も何も知らぬ空(うつ)け者!誰かおらぬか!このような者には冷宮こそふさわしい!」と怒鳴りつけた。
董鄂妃はひどく恐れ、順治皇帝は弁護しようにも言葉が出ない。
宦官(かんがん)たちがやって来て董鄂妃を小突きながら出て行ってしまう。順治皇帝は、皇帝の威厳も何もかなぐり捨てて母の前に跪き、赦しを請う。
それでも孝荘文皇后の怒りは一向に収まらない。哀れな順治の様子を横目で見るも、終(つい)に一言もなかった。
****** ****** ******
紫禁城内。
ひっそりと暗い、冷宮の中。
董鄂妃の肖像が生き写しのよう。だが、額の部分が白い紗に囲まれている。
数名の僧侶が宦官たちの監視の中、弔いの儀式がひっそりと執り行われている。順治帝は喪服に身を包み、呆然と立ちすくんでいる。
老僧が、数珠を繰りながら帝の傍に来て、柔らかな声で慰める。
「陛下、お気を落とされませんように。来るも縁、去り行くも縁と申します」
「そうであるならば、もはや朕(ちん)には行くところがない。もう、生きたくもない」
「いいえ、陛下には行かれるべきところがございます!」
「どこへ行けと言うのだ?」順治帝が吐き捨てるように喚いた。
老僧が今度は声を潜めて言う。
「覚えておいででしょうか、陛下? 六根静まり憂いなきところを!一つが解決すれば全てが解決するというところを?」
「おお、出家か?そちの言わんとするところ分かったぞ。しかし、世界は広い、いったいどこへ行って出家すればよいのであろうか?」
「東南の方角に光が見えます。そこに隠元禅師がおられます。隠元が極めた奥義は、皆、ひとしく陛下のものではありませんか!」
「隠元とな?あの、求めれば必ず応えてくださると、誉れも高き隠元禅師のことであるか?」
「陛下ご賢察の通りであります。このうえは、もう機会を逃してはなりませぬ。ただし、聞くところによれば、隠元禅師は仏法の普及のため遠方へお出かけとのこと…」
順治帝はここで深々とため息をつき、感情を抑えきれずに言った。
「そちのおかげで、ようやく目が覚めた。天命を受け入れれば道は自ずと開けるものなのであろう。早速詔勅(しょうちょく)を下し、隠元を呼び戻そう!」
順治帝の供についていた宦官がこれを聞いて驚くが、そ知らぬふりをし、機を見て退いた。
事態は、切迫していた。
****** ****** ******
後宮、奥の院。
高位の宦官がお付きの宦官を伴い、孝荘文皇后に上奏(じょうそう)している。
「恐れながら、皇太后様に申し上げます。皇帝陛下がご出家をお考えであそばします。詔勅を下し、南方に住む高名な僧侶、隠元禅師を探しておられます」
孝荘文皇后は椅子から転げ落ちんばかりに慌て、
「なんと、陛下が出家?それは一大事じゃ。このうえは本(もと)を断って抑えなければならぬ。すぐに刺客を放ち、隠元を殺せ!」
「仰せのとおりに!」
居並ぶ宦官たちが応じた。
風の強い夜更け。
都の郊外の大通りを、あの老僧が時折後ろを振りかえりながら馬を駆り、猛進している。
老僧は、右前方に小さな林があるのを見つけると手綱を引いて馬を下り、林に分け入り、こっそり身を隠した。実は老僧こそ、郊外の「大仏寺」大僧正その人なのであった。
ほどなく、地を揺るがすほどの蹄(ひづめ)の音と馬のいななきが聞こえ、大路に土煙が立った。清の騎馬兵が数騎、駿馬(しゅんめ)を駆って走り去っていく。
所変わって、こちらは大仏寺の門外。
老僧と、修行僧に扮した万里の長城「喜峰口」の守護将軍、朱虎が別れの挨拶を交わしている。
老僧が言う。
「もはや北方は清の天下。明朝復興の道は茫漠たる彼方にある」
「南明に向かうにあたり、尊師様に命がけで救っていただいたこの御恩、一生忘れません」と朱虎。
「このうえは、ただ鄭成功に望みを託すのみでしょう。時に、隠元禅師については良い噂が伝わっています。このたび日本へ渡り、仏法を伝えることになったらしい。将軍にもし御縁があれば、ともに手をば携え、困難を乗り越えていくことができるかも知れません」
「尊師、お言葉しかと胸に刻みました。では、これにて!」
****** ****** ******
「和尚さん偉い!でも、隠元さんを追っかけてくるのね!」
麗ちゃんがまた心配そうな面持ちになった。
「隠元さんの一行三十余人は、もうそのころ福建省厦門(あもい)の港に到着しているよ。鄭成功大将軍がしっかり護衛してくれていたからね。日本に向けまもなく出航するところだ」おじいさんが、にっこりそう話してくれた。
「ああ、よかった!それならいじわるな太后も何もできないわね!」
「そうとは限らないさ。殺し屋を送っているんだもの。日本まで追いかけてくるかもしれないよ」と翔くん。
「ようし、それじゃ続きを見ていかなきゃいけないな!」
おじいさんがますます乗ってきた。
第十六話
厦門港の波止場―古くは「中左」と呼んだ―には商船の帆柱が林立し、活気に満ちていた。
港の近くに海に面して聳(そび)える高台があり、頂上には奇妙な形をした岩石群が重なり合い、互いに支え合うようにして立っていた。
鄭成功、黄道周と隠元が三人そろってここに登り、見事な景色に感嘆の声を上げている。
太鼓を交えた楽(がく)の音(ね)が、坂の下から聞こえたかと思うと、数百名の鄭家の兵士たちが列を作って登ってきた
岩石群のほぼ真ん中にとりわけ大きな岩が聳え立っていて、「仙巌」の二文字が刻まれていた。非常に厳(おごそ)かな雰囲気である。
その岩の正面に祭壇が設けられており、供物や墨や硯(すずり)が置かれていた。
やがて、ちょうど三十六人の兵士が列から歩み出て高台の頂上に登り、楽の音に合わせて「周礼佾舞」を舞い始めた。
踊り手たちは列を組み替えながら、次第に鄭成功たちを中央に導き、取り囲んでいった。
鄭成功大将が、両手を大きな岩に向け、
「神が仙岩を挙げて波を鎮める(神挙仙岩鎮惊濤)」と唱えると、
「雄雄しき忠誠の心を天は知りたもう(壮心赤胆天公曉)」
黄道周が天を仰ぎ、これも流暢に唱えた。
隠元は、萬福寺を出発したときの情景を思い出し、感情の高ぶりを覚えた。
そして、目に涙を湛え、こう続けた。
「しばし故郷の十二の峰々を離れん 青空が広がり 雲が消ゆる頃帰り来たらん」
三人の詩文をまとめて唱えると、
神挙仙岩鎮惊涛
壮心赤胆天公曉
暂离故山峰十二
碧天云尽归期報
となったのである。
辺りを覆う覚悟と気概。
すると、隠元は身を翻(ひるがえ)して祭壇に向かい、筆を執り、豪快に、大きく「禅」の一文字を書いたのだが、思わず最後の縦の一筆を長々と下へ伸ばしたのであった。
鄭成功はこれを興味深げに見ていたが、すぐに笑い、
「禅師殿、もう十分でありましょう!」と言った。
隠元は、まるで突然正気に戻ったかのように、すぐさま筆を置き、手をぬぐうと、やや自嘲気味に微笑み、その書を鄭成功大将軍に贈った。
鄭成功、これを恭しく両手で受け取り、
「禅師殿の書かれた「禅」の一文字、ありがたく頂戴します。代々の家宝として大切にいたします。」と謝辞を述べた。
****** ****** ******
「国(こく)姓爺(せんや)」と記された巨大な船体と三本の帆柱は、波止場の船の中でもひと際人目を引いた。若い僧侶たちが、忙しく船に大量の荷を運び込んでいる。
鄭成功が、国姓爺号の傍らで別れを惜しんでいる。隠元は合掌して謝意を表しつつ、以前鄭が言っていた「母御への文(ふみ)」について如何と訊ねた。
すると鄭成功は微笑んで、傍らの、商人に身なりをやつした屈強な大男を指し、
「この男は鄭彪と申します。わたくしの母が彼を禅師のお伴にと寄こしたのです。道中護衛にもなりますし、母たっての願いでもあります」
こう言うと、近衛兵の手から受け取った四角い紫檀の礼盒(贈答用の箱)を、隠元に手渡したのだった。
隠元、謹んで礼盒を受け取ると、箱の蓋に金箔装飾で刻まれた「縁(えにし)」の文字をじっと見つめた。
鄭成功はこれを見て、目を細め、
「禅師殿!縁。この世で結ばれた縁は、永遠に続きます!」と言った。
隠元も感じ入って、
「大将軍殿のお心遣いに感謝いたします。まさに至れり尽くせりとはこのこと」と涙した。
「禅師様、道中のご無事をお祈りします!深い縁で結ばれた者同士、三年後にはきっとここでまたお会いできましょう!」
今度は、黄道周が思いを込め、豪快に言うのであった。
ほら貝の合図で、国姓爺号が三本のマストいっぱいに風を受けて出航する。
福州号の船主であった何素如が国姓爺号の舵(かじ)取りの位置に着き、片手でしっかと舵を取り、もう一方の手で別れの挨拶をしている。
国姓爺号は、舵が繰り出す水しぶきで海面に長く白い航跡を残しつつ進み行くのであった。
第十七話
一六五四年六月半ば。
東海(東シナ海)は風が強く、波が高かった。
国姓爺号が強風と高波の中、はげしく揺られている。
船に乗っている大方の者が船酔いで苦しみ、あちらこちらで身体をくの字に曲げていた。
隠元は、「薬」の字が記された木箱を開けさせ、独立性易が中から取り出した丸薬を受け取ると、禅杖で安定を保ちながら大またで歩き、嘔吐している者たち一人一人の口元に薬を持って行き、呑ませてやり、その背中をこぶしで叩いて回った。
舵手の何素如が波をかぶりながらも、必死で舵を握り続ける。
力持ちの弟子木庵性瑫と鄭彪も駆けつけ、両手を差し出して少しでも安定させようと舵取りを助ける。
隠元は船室に入って座すと、弟子大眉の手からあの亀を入れた籠を受け取り、前に置き、目を閉じて心を静めている。籠の中の亀は明らかに大きく成長している。亀も、じっと隠元の顔を見上げたまま動かぬ。
****** ****** ******
おじいさんは、ここで以前に読んだ『亀の唄』を思い出した。
隠元とかかわりがあるだけでなく、そもそもとても良い詩であった。
言うと麗ちゃんと翔くんも聞きたがったので、おじいさん、喉の調子を整えて、軽く唸(うな)りだした。
大きくなったね
わたしの小亀
もう幾年も 一緒だね
みなは言う
お前には 思いがないと
それでもわたしは 知っている
お前の裡(うち)にある たくさんの思いを
ずっと離れず これほど愛着が湧くのはなぜ?
固い甲羅の内に 温かい心を秘めているから!
歳月と風雪で
いつしか 少年だったわたしも白髪に
わたしたちは 知っている
永遠に過ごす 共にある日々
****** ****** *******
狂ったような暴風が、高波と共に船を襲う。
独立性易が慌てて船室にやって来て、迫りくる危機を報告する。
隠元はその声を聞くや、目を挙げて周囲を見回す。そして、突然両目を大きく見開くと、籠の中の亀をじっと見つめた。
「弟子よ、筆と墨をすぐに用意しなさい!」
船は揺れ続けていたが、弟子の大眉はしっかりと立ち、膝を曲げ、「字」と書かれた箱を開け、筆と墨を取り出すと師匠に渡した。大眉はなおも進み出て片膝をつき、一枚の紙を膝の上に敷いたのであった。
隠元は何事かを唱えながら亀の入った竹籠を大眉に渡し、筆を揮(ふる)い、「免潮」の二文字を書くや、紙を丸め、香で焼き、すぐにその灰を大海原に投げ込んだ。
船上の全ての人々が必死の奮闘を続けていた。
ある者は水漏れを塞ぎ、またある者はびしょ濡れになりながら水を汲み出していた。
どのくらいの時間が経ったことであろうか。
やがて、さきほどまでの狂風が収まり、波も次第に穏やかさを取り戻していった。
水面を飛ぶ魚たちの姿も見え始めた。
張り詰めた緊張と戦いの後、生気がふたたび船中に戻り、お互いの無事を喜び合う姿が其処此処に見えるようになった。
弟子たちは合掌し、お互いに慰め合い、思わず知らず隠元禅師を敬い、これぞ生き仏なりと口々に叫んだ。
隠元は大眉の手から竹籠を受け取ると、亀を出してそっとなでながら、
「竜王が道を譲ってくれたのはお前が教えてくれたおかげだよ」と言うや、亀を見つめながら、
「わたしとお前はもう数十年も一緒に、雨の日も風の日も、同じ船で旅を続けてきた。まこと、深い契りで結ばれているの」と言った。
弟子たちはそれを彼らなりに解釈し、
「数十年も、まるで一日のようです。禅師様の恩の深さには、誰もが感じ入っております」と唱和した。
「報いを求めず恩情を施せば、天下に平安がもたらされることだろう。この先も道は長い。よくよく気をつけて参ろう」と隠元。
これを聞き、それぞれ大きく頷き、各自の持ち場に戻ったのであった。
****** ****** ******
その日は、雲一つない青空であった。
国姓爺号の東側の海上に、三艘の船影(せんえい)が現れた。
それらはやがて舳先(へさき)をこちらに定め、みるみる近づいてきた。
船乗りどもの姿かたちが分かるほどに近寄ってくると、先頭の黒い船の舳先に、色黒の大男が股を広げて立ちはだかっているのが見えた。
男は、指の欠けた黒い手を高く掲げ、北方訛(なま)りの中国語で大声をあげた。
「同胞よ!おれたちはただこの乱世に行き場を失っただけだ。寛容な心で金子(きんす)の袋を投げて寄越してくれ!さすればお互いそれぞれの道を進めるであろう!」
これに、舵取りの何素如が大声で応えた。
「黒い親分さん!いまはもう昔とは違う!諦めなさい!」
黒い親分、ここで引き下がるはずもなく、
「おお、そうかい!ならいいや!ものども!遠慮は要らねえっ!かかれっ!」と大音声に呼ばわった。
言うが早いか、海賊どもは国姓爺号に向け、鉄の鈎(かぎ)がついたロープをつぎつぎと投げかけ、鉤先が船べりを捉えるや、猿のようによじ登って来た。
ところが思いがけないことに、船には上半身裸になった屈強な僧侶たちがとっくに整列して待ち構えていたのだった。
僧侶たちは、もとより文武両道を鍛え抜いている。
登って来た海賊どもに当て身を食らわし、あるいはこれを投げ飛ばし、当たるを幸い、片端(かたはし)から海に投げ込んだ。
あちらこちらで、海賊どもの悲鳴と水音が上がった。
戦いを指揮する黒い親分は、予想と全く異なる事の成り行きに面食(めんく)らい、ヒステリックに声を張り上げ、手下らに登れ、登れとけしかける。
このとき、隠元が早足で帆柱に向かった。
その後ろにぴったりとつき従う鄭彪が「礼盒」を捧げ持っている。
鄭彪は禅師が頷くのを見て、箱から畳んだ錦織を素早く取り出すと、するすると帆柱をよじ登り、柱を両足でしっかり挟むと、手を伸ばして錦織を開き、「鄭」の文字が織り込まれた旗を広げた。
大将軍の威厳溢れる錦の軍旗が海風に吹かれ、ひゅうひゅうと音を立ててはためいた。
黒い親分は「鄭」の大きな軍旗を見定めると、顔色を変え、水に落ちた手下を引き上げるなり、大急ぎで遁走(とんそう)していった。
難を逃れた国姓爺号の帆柱の下では皆が隠元を囲み、口々に、
「禅師様はまたしても我らをお救いくださった。まことに神のよう!すべてお見通しではないか!」と称賛してやまなかった。
隠元は、鄭彪が帆柱を滑り降りてくると、その頑丈(がんじょう)な肩をたたき、
「阿弥陀仏!わたしが見通したわけではない。長年の壮絶なご経験により海路の危険を知り抜かれた鄭将軍がお備えてくださった賜物のおかげ!しかも、こうして鄭彪を伴に遣わしてくださった。これこそ、的を得たご手配と言わずして何と言おう!」感慨ひとしおに、言うのであった。
ラッパの音が響き、国姓爺号は再び、一路日本を目指すのであった。
第十八話
一六五四年七月五日朝。
国姓爺号は、ついに長崎に到着した。
船体は長い航海で風雨と荒波に晒され、傷だらけはあったが、隠元は身なりを正し、しっかりとした足取り。歩くたびに、禅杖がこつこつと音を立てている。
随行の弟子たちも、身なりはぼろぼろだが、それぞれに勇ましい姿であった。明らかに、航海中の過酷な経験が、仏法伝授の使命を帯びた僧侶たちを尚(なお)さらに練磨していた。
港は、明の高僧を歓迎するため集まった役人、僧侶、農民、商人たちでごった返していた。
太鼓やラッパが鳴り響き、伝統的な日本の舞踊や歌もありで、人々の歓迎の気持ちが十分に伝わった。
はじめに、「興福寺」の華人住職逸然禅師が数名の弟子を従え、仏教の作法で、隠元一行に挨拶しにきた。
逸然は隠元に深々と辞儀をすると、
「禅師殿におかれましては、このたび艱難辛苦を乗り越え、はるばるご光臨くださり、日本国は帝(みかど)から庶民に至るまで皆々大喜びでございます」と語った。
逸然は、続けて、傍に控えている侍を紹介し、
「この方はこの地方の代官様であられますが、幕府の特命でお迎えに来られたのです」と言い、今度はその代官に向き直り、日本語で通訳するのだった。
代官はすぐさま進み出て、
「禅師殿にお目にかかれて光栄至極です。拙者は幕府(こうぎ)の命を受けて参りました。徳川将軍家からの親書を携えて参りましたので、謹んでお渡しいたします」と挨拶するなり、従者が片膝を地に着けて捧げ持つ金箔のちりばめられた漆器の盆から書簡を取り出し、隠元に手渡した。
逸然が、隠元の傍らで逐次通訳していく。
隠元は禅杖を抱え、両手を合わせると、書簡を受け取り、開いて読み、満足の表情を浮かべた。
訪れる側も、迎える側も、互いに家族の様な親近感に結ばれ、楽の音の中、列を成して興福寺に向かうのであった。
ただ、人垣の後方にいた数人の西洋人商人たちだけは何事かを囁(ささや)き合い、暗い面持ちであった。
****** ****** ******
一六五四年七月十八日。
南国の厳しい陽射しが降り注いでいた。
興福寺本堂の脇に、三層の石段を備えた三つの平台が用意され、すでに数百名の信徒がこれを埋め尽くしていた。
僧侶や信徒たちはそれぞれに異なる装束に身を包んでおり、いくつかの四角い陣を組んで整列し、本堂の入り口を見上げている。
やがて、隠元が袈裟をまとい、ゆっくりとした足取りで本堂から出て来た。
後ろに、大眉性善、独立性易、木庵性瑫らがぴたりと付き従っている。
まずは逸然が、主宰者として挨拶を述べた。まことに流暢(りゅうちょう)な日本語である。
「本日吉日、ついに、天下の名僧隠元隆琦禅師をお迎えすることができました。これは興福寺の幸いであり、長崎の幸いであり、日本国の幸いであります。これから、講話の場を設け、禅師の教えを聴くことができます。かならずや、多くの難題が解き明かされ、廃(すた)れていたものも復興することでありましょう!」
何素如は隠元のそばに立ち、汗を拭いながらその意味を伝えていたが、逸然の言葉が終わりに近づくと、隠元の袖を引っ張って、「禅師様、あなたの番ですよ」と促した。
隠元は、ゆったりとした動作でうごき、よく通る声で、
「阿弥陀仏!仏の光が普く照らし、天下の幸いが成就しますように」と語りはじめた。通訳にあたるのは、やはり逸然である。
****** ****** ******
会場を埋め尽くした聴衆が喜びに沸き、講話に聴き入っていたときのことであった。
一人の大柄な西洋商人が突然後ろのほうから石の欄干に跳び上がり、西洋訛りの日本語で隠元の講話を遮(さえぎ)ろうとした。
「皆さん!この世は神が創られました!東洋も西洋も同じ家族です。通商を公平に行えば、互いに友情で結ばれます。新しい道を歩んでこそ王道楽土が得られます!いつまでも古い教えに従っていては永遠に苦しむだけです!」
すると、示し合わせていたかのように、聴衆に紛れ込んでいた西洋商人たちがつぎつぎに野次を飛ばし、この時とばかりにかき乱したので、遂には耐え難いほどの騒がしさとなってしまった。
逸然は急いで前のほうに駆けて行き、大きな声で、静かにするよう説き始めた。「信者の皆さん! 聞いてください!仏は常に道理を説いておられるのだから!」
怒号、叫び、罵声(ばせい)が飛び交う。
混乱の中、西洋の商人たちは手分けして群衆の中に入っていくと、言葉巧みに誘導し、多くの聴衆を解散させた。
騒動がようやく静まった時、興福寺の会場には僧侶たちだけが残っていた。
講壇の傍らで、まことに気まずい面持ちの逸然が、隠元一行に詫(わ)びている。
「皆様方、どうかお許しください!まったく予期せぬことだったのです!」
「悪いのはあの西洋の商人たちです!」と木庵。
「彼らがこんなに焦っているのは、我々が通商の道を断って、彼らの生活を脅かすとでも思ったのだろうか?」と大眉が続いた。
「確かに、長崎が開港してからというもの、西洋人がやって来て一気に深く入り込み、思うままに振舞ってきましたから。近年ようやく江戸幕府が禁令を出し、日本の伝統を守ろうと動き出したのです。今回の催しは仏教の再興を促すためのものですから、西洋人たちが慌てるのも無理はないのです」と逸然。
「果たしてそうであったのか!そこで得心いたした!」
隠元は禅杖で地を一突きして、こう言うと、懐から徳川将軍からの書簡を取り出し、逸然に渡し、なおも続けた。
「有難いことに徳川大将軍様には先見の明がおありだ。わたしたちも本日、その意味をよくよく悟(さと)ることができたのだから、まだ決して遅くはないのだ」
逸然、隠元より当の書簡を受け取り、これを読み、
「おお、確かに。大将軍は、昨今の情勢を見るに、仏教は日々衰退し、民は拠りどころを失い、精神の危機にあると観ておられる。急ぎ手を打つ必要あり。禅師様には講壇を設けていただき、正しい教えを以て人々を導いていただきたいと。ああ!大将軍の言葉で深い霧が晴れました。これこそまことの名君!禅師様の真価をわきまえておられた。それにしても、禅師様がこれほどの大任を担わねばならぬとは!」
一気に、こう語った。
隠元は、逸然から将軍家からの書簡を受け取ると、これを高く掲げ、
「拙僧たしかにご命令を承りました。仏法を世界に広め、仏様の御恩に報い、世を大愛(だいあい)で満たしましょうぞ」と誓いを立てたのであった。
一同、感極まり、あたりは「阿弥陀仏!」の力強い唱和に満たされた。
第十九話
おじいさんの物語は、ここで小休止となった。
隠元一行が日本に来て、その入口であった長崎ですぐに西洋の商人たちの妨害に遭ったことなど、そもそも思ってもみなかったことだからである。
「ぼくは、殺し屋が追っかけてくるんじゃないかと心配だったの。まさか、西洋商人が嫌がらせをするなんてね!」
「こんなに大変なことばっかりで、それからいったいどうしたの?」
麗ちゃんも、気が急いて仕様がない様子だ。
「大丈夫だよ。怖がる必要はないんだ。「大愛」の二文字があるだろう?隠元禅師は心が寛いし、三十何人もの心を通わせる仲間がいる。どんな困難だって解決していけるよ」とおじいさん。
「そうだね!でも、あの鄭彪はなにしてんの?おっきくて、強いんでしょ?悪者なんかやっつけちゃえばいいのに!」と翔くん。
「だめよ!喧嘩はダメ!先生に怒られちゃうよ!」
おじいさんはカラカラと笑っている。
「よし、じゃあ、その鄭彪が何をしているか、そこからまた続けようね」
****** ****** ******
長崎、平戸。
こざっぱりしたレンガ造りの大邸宅。大きな門には「鄭氏」と刻まれた表札が掛かっている。
鄭彪が尋ねてきて、鄭家の家来の取次ぎで屋敷の奥に招き入れられた。
応接間には中国式の紫檀(したん)の家具が一式。八仙桌と呼ばれる正方形の机の上に、鄭成功の父である鄭芝龍の遺影が飾られていた。
鄭成功の母、田川マツはきちんとした佇まいで、和服を優雅に着こなしていた。マツは茶卓を挟んで鄭彪と向き合って座り、お茶を淹(い)れて語り合う姿は親子のように親しげだ。
鄭彪は、懐から鄭大将軍の書状を取り出し、両手で捧げ持ち、マツに渡した。
マツは封を切り、息子からの書状を読み終えると、長々とため息をつき、暗い表情となった。やがて立ち上がり、部屋の中を行ったり来たりしたかと思うと、墨と硯を取り、素早く手紙をしたため、鄭彪に手渡しながら言った。
「鄭彪君、大明国が危機に瀕しています。成功将軍の双肩(そうけん)に掛かった責任はまことに重大。事は急を要します。ご苦労ですが、すぐに京都へ行き、上様の側近であられる宮本様にお目通りし、この書状を届けてください。もう一度言うが、一刻の猶予(ゆうよ)もできませぬ!」
鄭彪は頷くと、書状を用心深く懐に収め、立ち上がり、すぐに暇乞(いとまご)いしたのであった。
****** ****** ******
京の都。
鄭彪が馬を牽(ひ)き、ゆっくり歩を進めながら、訪問先を探している。
市中の閑静な通りに大きな門があり、両端に宮本家の家紋を印した提灯が掛けられている。両側に門衛の侍が小槍を構えて立っている。
鄭彪は、ことさらに無礼が無いよう気をつけながら、書状を捧げ持ち、門衛にこれを渡した。
将軍家の側用人である宮本忠政が、使者を侍らせ、書状に目を通している。
老練な政治家であるが、文面を読み進めるにつれ、かすかに眉がひそめられていく。鄭彪は平伏しつつも、時折そうした忠政の表情を窺(うかが)い見て、額に汗を滲ませるのであった。
忠政はマツからの書状をしまうと、これについてはもはや触れず、
「鄭家からの使者殿、道中お疲れであろう。まずは、ごゆるり身体を休められよ。おって、上様にご報告申し上げるゆえ」と言った。
鄭彪、慌てて平伏し、
「どうか徳川将軍様のお慈悲を賜りますように! わが国は存亡の危機にあり、もはや一刻の猶予もありません。なにとぞ速やかに援軍を賜りたく!」と全身全霊で言葉を振り絞った。
忠政、正座のまま、双眼をなかば閉じんばかりに、
「おって沙汰する。本日は、まことにご苦労であった」と述べ、その場を去っていった。
****** ****** ******
江戸城。
四代将軍徳川家綱が、一通の書状に目を通している。
宮本忠正が、さきほど持ち込んだばかりのマツからの書状である。
家綱が読み終えた頃合いを見計らい、忠政が声を発した。
「上様、明国の命運まさに尽きようとしております。このような時勢に、軽率に兵を動かせば、弱きについて強きに立ち向かうこととなるは必定。ここは慎重にも慎重に動くことこそ肝心と心得ます」
家綱、しばらく考えて、
「その方の申す事、尤(もっと)もじゃ。ここは熟慮こそ肝要。鄭成功が東海(東シナ海)航路を護り、わが方の貿易船が安全に行き来できるのが理想ではあるが…」
家綱はこう言うと、マツからの書状を手元に置き、床几(しょうぎ)に身を預けた。
そうした矢先であった。
いまひとりの側近が、謁見の間に通された。
その者が言うに、
「上様、申し上げます。明国よりこのほど渡来した隠元一行三十余名、長崎にてすでに説法を始めておりましたところ、南蛮人らとの間で対立を生じ、少なからず騒乱まで惹き起こしたとのことにございます」
「左様か。詳しく調べ、その都度報告せい」と家綱。
忠政、あらためて、
「上様。火のないところに煙は出ない、と申します。かの隠元とやら、只者ではないように思われます」と言った。
「忠政、案ずるには及ばぬ。隠元が仏法を説き、仏教が復興すれば、政教合一で、国家にとっても民百姓にとっても利益になるはずじゃ。協力を仰ぐことができれば、幕府にとっても天の助けではないか!」
「上様、さすがのご賢察。恐れ入り奉ります。情勢よくよく掴み、その都度、ご報告申し上げます」
「天下は、いまこそ文治の時代に向かわんとしておる。とにかく、まずは平和の維持が肝心じゃ。鶏が先か、卵が先か。そのうちその隠元とやらにも会ってみたいものじゃ!」
家綱の表情には、穏やかな微笑みが広がっていた。
****** ****** ******
おじいさんは、地図帳をまた取り出してきた。
「明と清の交代期。内戦は避けられなかった。その一方、日本はすでに戦国時代が終わり、江戸時代の安定期に入っていた。第四代将軍だった徳川家綱は優れた青年将軍で、文治政治を敷き、隣国との友好平和を尊んだ。だから、社会も安定し、国民が安心して暮らせたんだよ」
「それじゃ、なおさら、明国が清国に対抗するために軍隊を貸して、なんて言ったって無理だよね!」と翔くん。
「お兄ちゃん、何でも知ってるみたいな言い方して。それなら、隠元禅師はどうしたの?」
「それは、おじいちゃんに聞きなよ。へへっ」
「おじいちゃんに聞いてもむださ。でも、隠元禅師なら、きっとこうやって妙案を出せたと思うよ!」おじいさんはそう言って、歌舞伎の役者がやるように見栄を切ってみせた。
翔くんも麗ちゃんも大笑いだ。
第二十話
長崎、興福寺。
人波が揺れ動き、あちこちに線香の煙が立ち上っている。
非常な賑わいである。
住職の逸然の姿が見える。
再び不測の事態が起こることを案じてか、こころもち緊張したような面持ちである。
今日は、説法の会を開くのであった。
朝早くから、信徒が続々と寺に詰めかけていた。本堂の外が、もう足の踏み場も無い状況になってきていた。
幕府より遣(つか)わされ、様子を見に来ていた者たちが、その中に紛れていた。
そのほかに、帯刀の侍たちが幾人かが、信徒の群れを遠巻きにしていた。
隠元は講壇に上がると合掌し、会衆に向かって深々と礼をし、顔を上げ、
「拙僧不才ながら、しばし皆様のお耳をお借りします。わたくしがここでお伝えする仏法は、凡(およ)そ全ての宗派を包含するものです。心を合わせ、同じ方向へ進めば、行き着くところもまた一つ所。心を合わせて助け合うなら、難業も成就いたしましょう」と語った。これを、逸然、丁寧に通訳する。
聴衆は静まり返り、全身で禅師の言葉を聴いている。
ある者が、突然質問した。
「和尚様、同心(心を合わせる)同心と世間でも良く言われるが、同心とはどういうことをいうのですか?」
隠元が、穏やかに答える。
「俗世間の功徳も、悟りの世界の功徳も共に励み、自分の喜びと、他人の喜びを共に喜ぶことです。儒家思想にも通じます」
すると、また問い質す者があった。
「禅師よ、あなたは儒家思想と仏教を一緒くたにしようというのですか?」
「儒家も仏教も、同源なのです。その源は、天下を覆う大きな愛、なのです」
隠元、少しも動ぜず、こう答えた。
「大いなる愛によりて、万物輝けん!」
逸然が、大きな声で、さらに一言を付け加えた。
人々が、思わず知らず、心の声を口にした。
「阿弥陀仏!天下を覆う大いなる愛!」
鐘の音が、長く響いた。
逸然が、隠元の手を引き、講壇を降りた。
すると、聴衆が、我に返ったかのように、二つの派閥を意識し始め、それぞれ主張し合って譲らず、激しく言い争いを始めたのである。
隠元は、弟子たちに護られて、自分の禅房に帰って来た。
逸然も付き添い、何事か、しきりに謝っている。
このとき、数名の武士たちがやって来て、自分たちは幕府から遣されて来た者であると告げ、併せて隠元に、しばらくこの不穏な土地を離れるよう勧めた。
隠元も先ほど来の様子を見て、ここは長い目で対処すべきと心得たので、数名の弟子を指名したうえで、武士たちと共に、ひとまず興福寺を後にすることにしたのだった。
第二十一話
大坂城。
言うまでもなく幕府直轄、西国の要である。
隠元は、側近三人の弟子とともに、家綱より招かれ、城内に居った。
隠元らが起居する部屋を中心に、厳しい警備体制が敷かれていた。大眉はその様子を見て、師匠にささやいた。
「お師匠様、ご覧ください。保護という名目ですが、事のところは軟禁ですぞ!」
独立も、気持ちを抑えきれない。
「お師匠様、どうしたらよいのでしょう?」
「こうなったらいっそ飛び出して行って、真相を訴え出てはいかがでしょうか!」木庵が焦って、思わず本音を漏らした。
たしかに、隠元らは外界から隔離されていた。
周囲はあくまで森閑(しんかん)としていたが、それが尚さら隔離の現実を身に染みて感じさせる。
時折、夜回りの拍子木(ひょうしぎ)の音が聞こえてくる。
いっぽうの隠元はというと、禅杖を手で弄(もてあそ)びながら、のんびりと構えている。
「はっきり言うのもいいが、ここはぼんやりするが上策じゃ。実のところ、ぼんやりするというのもなかなか得難い経験ではないか。いっそこの静かな環境を活かし、写経に励み、仏法伝授に備えるということではどうじゃ」と言った。
弟子たちはこれを聞いて、互いに顔を見合わせると、
「それもそうだ!ぼんやりできるというのも得難きこと!」と悟った。
やがて、おのおの携えて来た行李から経典の巻物を取り出し、写経に専念し始めた。
しかしこのころ、大坂城の城壁に、黒装束の人影がうごめいていた。
影は、静かに、目標に近づきつつあった。
****** ****** ******
順治皇帝が出家を望んだことは、すでに記した通りである。
このため、帝が派遣した密偵が大陸のあちらこちら、主だった城市に出向き、隠元の行方を探していた。
一方、孝荘文皇后は、皇室のスキャンダルを隠すため、刺客を派遣し、隠元の命を狙っていた。
それだけではない。
日本での独占的な商業利権を守るため、西洋の商人たちも、隠元たちの動きを逐一追っていたのである。
壁は大軍を押し止めることはできるが、人の流れを遮断することはできない。
刺客は影となり、夜の帷(とばり)に紛れ、その機会を伺っていた。
その夜も、隠元たちは、城の高い壁の内側で写経を続けていた。
蝋燭の芯が焼かれる音すら聞こえそうな、静謐(せいひつ)。
四人の筆から、端正な楷書で書かれた経文が次々と紡(つむ)ぎ出されていた。
隠元が、何かを思い出したようだった。
大陸を去る前に書きかけた、あの未完成の画仙紙を取り出し、広げて少し考えると、濃い墨を含ませた筆で、先に書いてあった「孤旌」の二文字の下に「独輝」という二文字を書いた。
ふと気付くと、文机の傍らにおいてあった亀の竹籠のふたが知らないうちに開いており、亀が籠の外に出てきて首をもたげ、ろうそくの明かりをじっと見ていた。
隠元はそれを見てにっこり笑い、亀に声を掛ける。
「まことに、あらゆる事物は単独では存在し得ない。お互いが引き立て合い、共鳴し合って生きている。「孤旌」と確かに書いたが、「独輝」など許される筈もないのじゃ」
大眉は、尊師が亀に話しかけるのを見て、笑みをふくんで、
「尊師よ、この書はいったい何時になったら出来上がるのですか?」と訊(たず)ねた。
すると隠元、亀を籠に戻しながら、
「全ての事どもに、「その時」がある。まことに瓜が熟して地に落ちるのも、天の摂理に沿っている」と答えた。
このときであった。
突然、外から、「曲者(くせもの)、出会え!」という鋭い叫びが聞こえた。
隠元らは、すばやく筆を収め、明かりを消した。
黒装束の曲者が、要塞のような大坂城に忍び込み、隠元の居室に突進して来たのであった。城内に内通者が居たであろうことは、疑いない。
賊の大方は、すでに斬られたようである。しかし、最後に残った大柄なひとりが、決死の覚悟で隠元の居室の襖(ふすま)を突き破り、転げ込んできた。
漲(みなぎ)る殺気の中、木庵が曲者と決死の挌闘を繰り広げた。
後ろから、大刀を構えた武士たちが飛び込んでくる。
そのなかで、隊長格の者が大声で言う、
「斬ってはならぬ!かならず生かして捕縛するのじゃ!」
木庵が黒装束の曲者を取り押さえ、その覆面を怪力で剥(は)いで見ると、その正体は、なんと金髪の西洋人であった。
第二十二話
大坂城を騒がした一味は、そののち江戸に移送された。
これは、家綱が直々に下問(かもん)することを望んだからである。
江戸城内。
老中から側用人まで、主だった幕臣が左右に居並んでいる。
大坂城に逗留中の隠元を、夜陰に紛れて襲った黒装束の曲者が縄打たれ、帯刀した武士たちに囲まれ、かしづいている。
「上様の御成り!」
第四代征夷大将軍徳川家綱が、あらわれる。
謁見の間に居並ぶ全ての幕臣、武士どもが、平伏する。
「面(おもて)を上げよ」
家綱が、口を開いた。
いよいよ、将軍家直々の下問が始まるのだ。
「長崎の港を開いたのは、世界諸国との友好往来のためじゃ。それなのに、そなたはなぜ、こうした我が国の趣旨を軽んじ、夜陰に紛れて我が国の客人の宿に闖入(ちんにゅう)し、あまつさえその命を奪わんとしたのか?」
金髪の西洋商人が、慌ててこれを否定する。
「上様、それはなにかの間違いでございます。手前どもも友好貿易の趣旨は重々存じ上げておりますし、上様のそうした御心に対し、日頃感謝の気持ちでいっぱいなのでございます。ただ、あの支那人の僧侶は、美言の裏にどす黒い欲を隠し持つ輩(やから)!後から来たくせにわたくしどもの縄張りを脅かし、生計を奪おうとしたのでございます。これゆえ、止む無く自衛策をとらざるを得なかったのです。つまり、こうする他、どうしようもなかったのでございます!」
すると、家綱は、今度はもう一人の黒装束のほうを指さした。
「その方はどうなのじゃ?見たところ、本邦人であろう?」
小柄なほうの黒装束は、
「上様、仰せの通り、わたくしは本邦人にて、恐れながら仏に仕える身でございます」と答えた。
家綱は眉をひそめ、今度はやや怒気を含んだ声で下問した。
「何と、その方、僧侶とな。仏に仕える身でありながら、なぜ幕府の意向、余の意向に逆らい、殺生を欲するのじゃ!」
僧侶はうなだれて、
「上様、どうかお怒りをお鎮めください!仏門には仏門の掟というものがありまする。例え理由がなくても、命令には従わなければならず、それを犯せば大罪にあたりまする」
家綱はいたく興趣をそそられた様子で、体を起こすと、自ら捕縛された者どもの方まで近寄り、穏やかな表情で尋ねた。
「ほう!それではその方、一体誰の命令に従い、何をしたのじゃ?」
僧侶はもはや観念している。
恭順(きょうじゅん)の意を示し、なにやら小声で語った。
すると、それを聞いた家綱が、今度は大笑した。
宮本忠政がこの様子をみて、いたく驚き、
「上様、いかがなされました?いかがあそばれましたか?」
そう言うなり、平伏した。
「忠政よ、そちもこちらに参れ!そちもこの者の言い分を聞いてみよ!」
家綱はこう言うと、さらに笑い声を響かせるのであった。
このとき、近習の一人が忠政の近くにまかり越し、何事かを伝えた。
忠政が居住まいを正し、家綱に言う。
「上様、かの隠元、すでに到着し、上様へのお目通りを待っております」
「そうか!着いておるか。よろしい。この者たちの処分はそちに任す。まずは、隠元と会ってみよう!」
ふたりの歴史的な出会いが、いま幕を開けようとしていた。
****** ****** ******
江戸城内。豪壮な中にも凛(りん)とした気が張りつめている。
家綱が、大老酒井忠勝はじめごく少数の幕臣に伴われ、隠元らが通された間に現れたのは、そろそろ陽の傾き始める刻限であった。
家綱、隠元ともに型通りの挨拶を交わした後、隠元が、まずは、大坂で遭った災難から救われたことについて謝意を表した。
幕府の通辞が隠元の斜め横で、一言一句、正確に通訳していく。
家綱は、第一印象で大変心を動かされたようであった。
「隠元禅師よ、その方のご高名、余もかねがね聞いておった。本日このような形で会うことができるとは!家綱、まことにうれしゅう思うぞ」
打ち解けた雰囲気となると、不思議と異文化の者同士でも通じ合うことが得てしてあるものである。
家綱と隠元が、しばしば片言の相手言語を話してみては、笑顔を交わし、大笑するので、通辞はそのたびに目を白黒させねばならなかった。
家綱は、先刻、黒装束の男たちから聞いた話を、かいつまんで隠元に伝えた。すると隠元、これには一方ならず表情を曇らせ、合掌し、慨嘆(がいたん)した。
「仏の教え、神の教え、いずれの教えも、人を赦し、大愛に生きることを勧めるもの。そうした教えを奉ずると自ら任ずる者たちの、あまりの狭量。排他性。まことに嘆かわしい限りにござります」
****** ****** ******
ところで隠元は江戸に滞在中、上州に養蚕製糸で名高い農家があると聞き、自らの少年時代を、また故郷の特産品を思い出し、視察に出掛けている。
これこそ、のちの「富岡製糸場」の前身である。
隠元は富岡の職人たちと盛んに交流し、行くところ行くところで温かな歓迎を受けた。隠元にとっても、異国での心温まる思い出となったことであろう。
家綱と謁見できたことは、その後、非常に大きな効果を生んだ。
家綱から大老酒井忠勝を通じ、心安んじて日本に留まるよう、またそのために京都付近に土地を選び、寺地をさずけよう、との意向が示されたからである。
隠元はやがてこれを受諾、竜渓の周旋(しゅうせん)を得て、京都宇治郡の一地方、大和田の地を寺基(じき)に選び、幕府から許可されたのである。ちなみにこの地は、御陽成天皇の女御、中和門院前子の別邸が置かれていた場所であった。
こうして万治二年(一六五九年)、つまり、長崎の地を踏んでから五年後に、隠元は十万坪にも及ぶ皇室ゆかりの地において、「黄檗山萬福寺」の建立に着手することとなったのである。
第二十三話
大坂。普門寺。
隠元の盛大な説法会が催されようとしている。
高い講壇が築かれ、匠や、それを助けて材料や品物を運ぶ者たちが忙しく行き来していた。
四方には、仏教の教えを印した旗や幟(のぼり)が飾られ、雰囲気を醸し出している。
さらに「芸」と書かれた大きな行李が開かれ、工具や道具がそこから取り出されようとしている。
講壇の右側にしつらえられたにわか仕立ての竹造りの小屋には、一幅また一幅と観音像の絵が掛けられ、大眉が、高いところに上って作業する若い僧たちに時折なにか指示を出していた。
講壇の左側の地面に敷かれた石板の上で、如来の彫刻像が刻まれていく。
范道生が厳しい眼差しで、石工たちの作業を見守っていた。
いつしか、隠元が范道生の傍らに来ていた。
隠元に気付いた范が尊師を拝礼し、微笑み合う。隠元は、説法会の準備の全てに満足している様子であった。
****** ****** ******
梵鐘が鳴り、普門寺周囲の肥沃な平野にこだました。
あぜ道といわず細道といわず、道という道に、整然と長い列を成して、僧侶や信徒たちが隠元の説法を聞きにやって来た。
彼らが手にしている旗印には日本各地の名刹(めいさつ)の名前が記されている。「遠く望めば、有徳の士を求め、福を求める」人々の熱気が充満していた。
これこそのちに「隠元詣(もう)で」と言われるようになる、当代の日本における隠元の絶大な影響力の一端を示すものであった。
来賓が、次々と壇に上がった。
将軍家綱、大老酒井忠勝より遣わされた幕臣が、講壇の傍で合掌し、席に着くや、会場が静まり返った。
隠元は講話を始める前に先ず幕臣に対して拝礼し、身を転じて講壇を降りると、木彫の如来像に向かい、何事かぶつぶつとしばらく念じた。
会場は、水を打ったような静けさである。
隠元は、数千人の聴衆に向かって、仏の教えを朗々と語り出した。
「日が東方に出ずれば、万物は光を生ず。御仏が天におわせば、恩寵は果てしない。禅の教えは明より伝来し、徳川幕府のご厚情を賜り、ここに万福の根を下ろし、扶桑(ふそう)(日本)の大地に信仰の種を蒔く」
ここで隠元は、会場を取り巻くようにずらりと並んだ木彫の如来像を示し、
「ご覧ください。天の恵みにより、木彫の彫像にさえ霊験が宿るのです。将軍様のおかげで、本日は全国各地の名刹より皆様をお招きし、黄檗の仏像をお持ち帰りいただき、仏の光で国中を照らすことが叶(かな)うのです。そして、本日を拙僧の特別な説法会、また、明国黄檗山萬福寺の来日を記念する儀式とすることができたのであります。これこそ、天下の大義であります!」
数千人の聴衆がこれを聞いて歓喜し、阿弥陀仏の声が高潮のように響いた。
梵鐘がまたひとたび打たれ、寺院の上空にこだまして、山林へと伝わった。
第二十四話
京都近郊、宇治山中。
雲が立ち、霞がたなびく神秘的な景色である。
山の坂道を、隠元と家綱が並んで登っている。
「尊師よ。今日は通辞もおらぬゆえ、遠慮は要らぬ。何事も気兼ねなく話をしようではないか」
「上様のご厚意、有難く存じます。まことに得難き機会。拙僧も同感です」
「それにしても、これほど短期間の間に、言葉の壁をなくすほど日本語を習得されるとは!まこと、尊師の才覚、尋常ではないのう」
隠元、あわてて謙遜し、
「恐れ入ります。我が国では、古(いにしえ)より英雄は少年より出ずると申します。上様こそ当代の英傑。現に、この山登りでは、拙僧遥かに後れを取っております」
二人は、穏やかに笑みを交わし合った。
家綱、ふたたび笑って、
「尊師よ、なにをおっしゃるか。顔も高潮しなければ、息も上がっておられない。まだまだお元気ではないか!」
そう言い終わらぬうち、足元の石段がたいそう高いのを見るや、隠元にすぐに手を差し伸べるのであった。
隠元もその意を解し、にこやかに禅杖を持ち上げ、先端を家綱が差し伸べた手に委ね、その力を借りて高い石段を登りきった。
二人はこうして語り合いながら山頂まで登り、四方を見回すと、大きく深呼吸をし、ともに景色を愛(め)でるのであった。
「帝より賜った土地じゃが、さすがに素晴らしき眺めじゃのう」
家綱が、一言、そう言った。
隠元は数珠を指でよっていたが、ここで、心の底の思いを家綱に打ち明けた。
「上様、拙僧、かならず上様のご期待に報い、仰せの通り寺を建て、来春には、開眼供養をいたします」
そう話すうち、隠元の目に涙が光り、声がやや震え始めた。
「さすれば、それが成就した暁には、どうか、上様の恩賜により拙僧を明に帰らせていただきたく!」
「なんと!寺基も定まった今になり、どうして暇を請うというのじゃ?」
家綱、あわててこう問うた。
「何を隠そう、明を出立の時、拙僧は三年を限りに戻るとの約定(やくじょう)で参ったのです。ところがもう五年が過ぎてしまいました。約定は必ず守らねばなりませぬ」
隠元としては、帰朝への思いを、遠回しに伝えたつもりであった。
家綱は感じ入って、一瞬黙ってしまった。
遠くを見つめていたかと思うと、天を仰いでため息をつき、
「尊師よ。そちこそほんものの尊師じゃ。信用を重んじ、必ず約定を守る。真に志有る者は何処にいても業を行うということか。さすれば、余が帝に奏上し、帝が父君、後水尾法皇にもお伝えし、きっと尊師の満足がいくようにいたそう」
こう語った。
隠元は深い慰めを感じ、
「上様のお心遣い、まことに勿体なく、恐れ入りましてございます。どうか天を覆う大いなる愛が永遠に続きますように!」
こう応じたのだった。
家綱と隠元がこのような話を交わしていると、山のふもとから家綱近習の者たちが「種」と記された行李(こうり)を担ぎ上げて来た。
隠元が行李を開け、一袋の種を取り出した。好奇のまなざしを向ける家綱に、
「上様、これはわが国の四季豆でございます。長く保存しても味が変わらないのです。どうか、この地に御手でお蒔きいただき、代々この美談をお伝えくださりますよう」と言った。
家綱は、四季豆の良種を受け取り、しみじみと、
「尊師のお言葉を借りて、四季を通じて春のようでありますように」と言うと、行李を担いできた者たちに命じ、土地を耕し、自らこれを蒔いた。
隠元は合掌し、何か念じていたが、突然声を高くし、
「阿弥陀仏、四季を通じて緑豊かでありますように!」と唱えたのだった。
****** ****** ******
宇治山中。
臨時に仕立てられた作業小屋があった。
隠元が、そのなかで新たに建立する寺院の設計図を広げている。標題には「山城宇治黄檗山萬福寺鳥瞰図」とある。
大眉ら弟子たちと仏像彫刻の大家范道生がその回りを囲み、あれこれと熱心に話し合っている。
范道生がしきりに首を振り、
「ここからさほど遠くない岡山一帯には良い石材が多いが、棟木と梁に使う楠木が足りない。こればかりはなんとしても明の南方へ調達しに行かねばなるまい」と言った。
ここで大眉が「妙案」を思いつき、手を打って叫んだ。
「先日ちょうど鄭彪に遇ったのだが、近く「福州号」に乗り、厦門港に戻り、鄭成功将軍に報告するのだと言っておった。彼に書状を託し、助けてもらってはどうだろうか?」
このときだった。
范道生が外から誰か入って来るのを見て、途端に笑顔になったのだ。
「噂をすれば影、とはこのこと!鄭彪大兄がいらっしゃったよ!」
鄭彪は、入ってくると笑いながら、
「皆さんおそろいで、またわたしの悪口でも言っていたんじゃないでしょうね?」と言うや、すぐに隠元を拝礼した。
すると、これまでは黙って傍で考え込んでいた隠元が力強く言った。
「天が黄檗を助け、萬福寺は必ず完成する!帰国する鄭彪に託し、鄭家の協力を仰ぎ、楠木を調達しよう!」
鄭彪は激情を抑えきれない様子で、
「そうとあっては、是非引き受けさせてください!」と答えた。
皆は大喜びで同意し、大眉性善と木庵性瑫は隠元に帰国の許可を請い、ともに大任を果たしたいと申し出、鄭彪と固く手を握り合った。
それから数週間後のことである。
福州号の舳先に船主の何素如が意気軒昂な様子で立ち、傍らにぴったりと鄭彪、大眉、木庵が立っていた。息を殺し、じっと波立つ海原を見つめている。
帆が風をいっぱいに受け、福州号は矢のように大海原の上をゆく。そして一路、東海の西、厦門港を目指して突き進んだ。
帰朝後、鄭彪は、鄭成功に対し、日本からの援軍を得る工作が不調に終わったこと、失意の底にあったそのとき、運よく明に戻る船に乗れたことを伝え、新たな対策を直ちに巡らす必要性を訴えた。
あわせて、隠元に協力するため楠木の調達に協力し、再び日本に戻り、大明の仏教建築と文化を日本に根付かし、発揚するべく協力したいと申し出たのであった。
****** ****** ******
「だけどね、この時期に明に戻るというのは、それはそれは危険なことだったと思うよ」おじいさんが、言った。
「でも鄭成功将軍を探せたってことは、黄道周軍師も探せたってことでしょ?」と翔くん。
「そうよ、それで、あの可哀そうな黄幽梅は?」ここはかならず押さえなくちゃと、今度は麗ちゃんだ。
「乱世だからね。なにしろ。みんな明日のことはわからない、っていう状況だったんだよ」
おじいさんは、そう、感慨深げに言うのだった。
第二十五話
江南の地は、血の海に盾が浮かび、広野あまねく屍(しかばね)横たわるような惨状だった。清の軍勢は大陸をまっすぐに南下し、ここに南明は完全に瓦解(がかい)した。
鄭成功は劣勢を挽回すべく奮闘したが、すでに希望は無かった。
鄭は残留部隊を率い、優れた航海術を頼みに台湾周辺へと逃れた。
一方、軍師黄道周は、故郷に帰り親族を救おうと、途中鄭成功に別れを告げ、馬に鞭当て、一路黄檗山に向かっていた。
そのころ、昔日「喜峰口」の守護将軍であった朱虎は修行僧の姿に身をやつし、鄭成功をたずねようと旅を続けていたが果たせずにいた。
朱が、ちょうど黄檗山の麓を通りかかった時のことである。
前方から馬を駆って猛進してくる男がおり、明の軍服を着ていたので、慌てて声をかけた。
黄道周であった。
黄は手綱を引き、荒々しく、
「この乱世に、なぜ道をさえぎるとはいかなる料簡(りょうけん)ぞ?」と怒鳴り、誰何(すいか)した。
朱虎、すぐさま拝礼し、
「こうするよりほか、仕方がなかったのです。お許しください。お訪ねします。我ら南明の将軍や兵士は今いずこ?」
「なぜそのようなことを?あなたはどなたですか?」
黄道周は驚くやら喜ぶやらで、問い返す。
朱虎、少しも慌てず、
「あなたのいでたちを見て、我ら大明の壮士とお見受けしました。炎黄の子孫であられますな?」
「あ、あなたは?」と言うや、黄道周も馬から飛び降り、
「あなたも、我が明軍の兄弟では?どこからおいでになり、どこへ向かっておられるのですか?」
「わたくしには罪があります!」
朱虎はそう振り絞るように言うと、懐から辺境への防衛将軍任命を示す金牌を取り出し、涙をこらえきれぬ様子で、
「わたくしは長城の喜峰口の守備将軍朱虎です。ここに任命の牌を持っています。しかし、関は破られてしまいました。ああ、この上もない恥辱に、もはやこの身のやり場もありません。これから南方に下り、鄭成功大将軍に従い、雪辱を果たそうと!そのためには死んでも惜しくありません!」こう語ったのだった。
黄道周は、この時点で、すでに明の敗亡が確定していることを知っていた。
それだけに心身とも傷つき果てた志士にすぐにはかける言葉がなかった。黄は、そこで、悲痛な思いをこらえてこう言った。
「朱将軍、わたくしと共に参りましょう。さあ、馬に乗ってください。明復興の首尾については、道中ゆるりと相談いたしましょう」
二人は、馬を駆り、突き進んだ。
巻き上がる土煙が、たちまちその姿を覆い隠した。
****** ****** ******
夕暮れ時になっていた。
天をも覆うような土煙、そして馬蹄の響き。南下を続ける清軍は、行く先々で残虐な蹂躙(じゅうりん)を続け、路傍の石まで砕き去った。砕かれた石は弾かれて流れに落ち、そのたびに一瞬、花の様な水しぶきが立った。
江南特有の湖と河が織りなす水郷風景。
夕焼けに照らされ、きらきらと輝く水面。そこをかなりな速度ですすむ一艘の小船が見えた。規則正しく漕いでいるのは、日本から海を渡り、楠木の手配をしに戻ってきていた鄭彪と大眉たち一行だった。彼らは清軍を避け、ひそかに南へ向かっていたのだった。
黄檗山麓。
燃えるような夕焼けが、荒れ果てた村落を赤く染めている。
昔日の黄府(黄家の屋敷)は見る影もなく、崩れた壁の脇に古い馬車が停めてある傍らで、黄道周が、すでに還暦を迎えた黄幽梅を支え、馬車に乗せようとしていた。
車夫や使用人が、それぞれの持ち場に就いていた。
同行する朱虎は二頭の大きな馬を牽いて側に控えていたが、黄道周が迎えに来ると、黙って一本の手綱を手渡した。
「戦乱の世にありながら、家人を抱えこの有様。まことにお恥ずかしい限りです。」と黄道周。
「黄軍師殿、何を言われる!戦に敗れ、家を失えば、誰もが同じ境遇になります。今後の道中、お互い腹を割って、何でも遠慮なく言い合いましょう。馬を駆り、共に行くからには、ただ前進あるのみです」と朱虎が応じた。
ここで黄道周は、一通の書状を懐から取り出し、朱虎に渡し、
「朱虎将軍、この先は長いし、行く先何があるか分からない。万一のときはこれをお願いしたい。いまひとつ…」
朱虎は書状を受け取り、
「黄軍師殿、どうか何なりとおっしゃってください!」
黄道周は馬車を指差し、
「わが妹の人生はまことに不遇。御縁あって日本へ渡ることができるのであれば、これは朱将軍に託すほかありません」と言うや、抱拳の礼をし、目を伏せた。
その目は、涙で濡れていた。
朱虎はそれを見て、どうして良いか分からず、慌てて同じ礼を返し、
「かしこまりました。命に代えて!」と応えた。
あぜ道が交差するひっそりとした村落には、もはや炊事の煙も絶えてない。
軍馬の轟(とどろき)が遠方より次第に近づき、旗が風に翻る音と共に、清軍が疾風怒濤の勢いで村を通り過ぎていった。
黄道周一行は、やがて三叉路に行き当たった。
これからまさに、進む方向を見定め、道を選ぼうとしたとき、朱虎の馬が何か気配を察したかのように突然足を止め、その場でぐるぐる回り始めた。
朱虎が、異変を感じた。
「黄軍師殿、ご覧ください、この馬はわたくしと長年苦楽を共にしてきましたが、とても勘が良いのです。前に進まないのは、きっと何か異常があるに違いありません!」
黄道周は、ここが潮時と直感した。
「そうだとしたら。万一に備え、ここで分かれて別々の道を行きましょう。またきっとお目にかかれます」
そう言うや、馬を下り、朱虎と手綱を交換し、
「将軍の白馬は道を知っていますから、かならず合流の場所へ連れて行ってくれることでしょう。あなたは左へ、わたくしは右へ。ここでお別れです!お託ししたこと、なにとぞよろしくお願い申し上げます!」
言うが早いか、黄道周、馬にまたがり、右の方向へ疾風のように走り去った。
取り残された朱虎は、交換した黒馬の手綱を牽きながら、ようやく正気を取り戻し、独り言のように、
「わたくしは左へ、海岸へ向かう。黄殿は右、反対方向だ。どうやって合流すると言うのだ?おお、そういうことか!託されたこと、機を逃してはならん!」
そう言うと、馬車に乗っている黄幽梅に頷きかけ、海辺に向け急ぐのであった。
夜の帳が、ゆっくりと降りて来ていた。
黄道周がまたがる白馬は、月光を浴びて奔(はし)っていた。目を見張るほどの駿馬であった。
しかし今宵の黄道周は、もとより生きるために走っていたわけではなかった。清軍に執拗に追われながら、偉大な軍師は、最後の力をふりしぼり、追っ手を引き離すため、走りに走り、最後は壮絶な殉死を遂げたのであった。
その黄道周の最後を目撃していた者たちがいた。
黄檗山の山中に身を潜めていた鄭彪ら一行である。鄭彪らは悲憤にさいなまれつつも、急いで軍師の遺骸を埋めた。そして、日に夜をついで河の岸辺へと向かい、小船をいかだに乗り換え、楠木調達の使命を果たすため、目指す雲南の密林へと南下していった。
****** ****** ******
台湾海峡の波は高かった。
大陸側の海辺の道を、頭を垂れながら、黄道周の黒馬の手綱を牽いて歩く朱虎の姿があった。後ろには、黄幽梅を乗せた馬車が続いている。
朱虎は、沈鬱な面持ちであったが、突然手綱を捨てると、大股で砂浜に踏み出した。水平線に点々と浮かぶ帆船を遥かに望みつつ、やがて両膝を地に着けて跪き、両腕を高く挙げ、天を仰ぎ、地に頭を打ち付けんがばかりの大声で叫んだ。
「天よ!わたくしは朱家の末裔として、辺境の関を奪われたことにはおおいなる責任があります。ですが、いま一度、わたくしが鄭成功将軍に従おうとしても一向道が開けないのはなぜでしょう?」
波濤(はとう)が朱虎の膝まで押し寄せ、まるで共に啼(な)いているかのようだ。
海辺の道の馬車の傍には、黄幽梅が立っていた。
朱虎が跪いて天に訴える姿を見、悲痛な叫び声を聞いて、幽梅もまた涙を流していた。
しかし、彼らの後ろには、新たな運命が拓(ひら)けてきていた。
朱虎と黄幽梅の後方から、福州号の船主何素如の姿が近づいていたのだ。
何素如のすぐ後ろに大眉もいた。やがて、湾の入り江に停泊する福州号の姿も望見できるようになってきた。
かつて、黄家の屋敷で出会った縁ある者たち。
歳月は、全てを、変える。
おのおの、目に深い悲しみを湛え、皆で静かに砂浜の朱虎を抱き起こした。
福州号は、錨を上げ、帆を風で膨らませ、東海の岸、戦乱の地を離れ、再び、一路日本への船路に就いたのであった。
第二十六話
山城国。
山城国宇治郡では、萬福寺の建立が進みつつあった。
槌の音が響き、石工たちが忙しく立ち働いている。范道生が、すでに形の出来上がった大小の石仏の間を丁寧に点検して回っている。
隠元はといえば、数名の弟子たちを後ろに従えて、指先で数珠をよりながら、経文を念じ、すでに完成した一体の大きな如来像に金箔を施していた。
そうしたところへ、手に棍棒を構えた無頼僧の一群が突如襲って来た。
その中の首領らしき僧侶が、隠元の目の前に迫り、激しい口調で罵(ののし)る。
「お前さんたちは、善悪をわきまえず、先に仏像を造り、後で寺を建てるという。仏の忌み嫌う過ちをわざわざ犯すとは何事じゃ!」
隠元は相手のすさまじい剣幕を見て、その程度を見極めるため、先ずは丁寧な言葉遣いでやんわりと答えた。
「お互い同じ仏に仕えるもの同士、拙僧とて本末転倒は願いません。ただ、棟木や梁の楠木の木材が着くのを待つ間を惜しみ、準備をしているのです。本日皆様の良きご指導を頂き感謝します。これからはご意向に背かぬよう、順序正しく進めてまいりたいと存じます」
隠元はその一方で、傍にいた弟子の独立に素早く目配せした。
独立は、怪しげな気配を見て取ると、お茶を取りに行く素振りを見せながら、その場を離れた。
無頼僧の首領は手を振って左右の者に声を掛け、なおも咆哮(ほうこう)した。
「つべこべ言うな!もともと寺など建てる力も無いくせに。とっとと山を下りて失せろ!」言いながら、首領は手を伸ばして隠元を指差した。
隠元が両目を見開いてその伸ばされた黒い手を見ると、指が欠けていた。
一瞬、あの海賊のことを思い出す。
指欠けの首領は隠元の鋭い眼光に射すくめられ、こちらもまた、あのとき東海で出遭った憎き相手と思い出したようだった。旧仇新恨入り混じり、大声で、それ打ち壊せ、と呼ばわった。
無頼僧たちも口々にはやしたて、棍棒を振り回し、隠元たちに襲い掛かった。 あわよくば山から追い出し、これを横取りせんとばかりの勢いである。
しかし隠元、この程度の暴威には少しもひるまず、喝を入れた。
「待たれよ!そのほうども、萬福寺とよくよく知っての上での狼藉(ろうぜき)か?もはや天罰すら恐れぬというか?」
首領はひるまず、ますます凶暴さをあらわにして言った。
「なんの!仏像など皆まやかしじゃ!何が天罰だ?片腹痛いわ。者ども、支那の坊主どもを追い出せ!思う存分やっちまえ!」
ここは柔を以って剛に対処するしかないと見た隠元は、素早く一歩踏み出し、まずは近くに迫った輩に気を発し、これを跳ね飛ばした。弟子たちは、師匠の動作を合図とみなし、それぞれに声を出し、気を発し、八卦の陣を構え、仏像を守らんと鉄壁の陣を敷いた。
無頼僧たちは、すでに明僧たちの圧倒的な気魄を前に、足を竦(すく)ませつつあった。そこで、首領がまた必死で叫ぶ。
「支那の坊主など恐れるに足りずじゃ!者ども、やっつければ褒美をとらせるぞ!」
無頼僧たちが再度攻撃を仕掛けようとしたちょうどそのときだった。
独立性易が馬を駆って先導し、幕府の騎馬武者たちが駆けつけたのだ。
見れば、側用人宮本忠政の一行である。
陣羽織を着込んだ忠政みずから、馬上で太刀に手をかけ、無頼僧どもに向かい、大音声で一喝した。
「皆の者、控えおろう!いやしくも上様の賓客隠元禅師に狼藉を働くとは不届き千万。よくよく仕置きをいたすゆえ、神妙にするがよい!」
無頼僧たちはこれを聞くと、まるで蜘蛛の子を散らすが如く、逃げ去っていく。しかし逃げ遅れ、捕縛された数名の中に、忠政は意外にも、江戸城で将軍家綱を失笑させた地元山城の僧侶がいるのを見つけた。忠政もこれには呆気にとられ、
「そのほう…どうしてまたそのほうがまたここに」とようやく言った。
僧侶は、忠政の前に平伏しつつ、
「なにとぞ、なにとぞお赦しくださいますよう!拙僧も、けっして故なくここに参ったわけではござりませぬゆえ…」
「なんと!この期に及んでまだそのような苦しい言い訳をするのか。先に上様に何と申した?もう一度言ってみよ!」
忠政の顔が、いくぶん上気している。
地元の僧侶は、おそらくすでに観念したのであろう、ふざけた調子で、
「明の皇帝がやられたのがいけないのです。そこでこの坊主も命惜しさに逃げてきた。この国でまた良い目をみれるかもしれぬと!宮本様、こやつこそ欲得狙いの似非(えせ)坊主ではありませぬか!」
こう言った。
「くどくど申すな!そもそも、隠元禅師とうぬらに、如何なる因縁があるというのじゃ?」
地元の僧侶は、ここいら辺が落としどころと見た。平伏したまま、声を落とし、こびへつらって、
「殿様、このたびは拙僧の不明の致すところ。どうか寛大なご処置を賜りまするよう!もとをただせば、この世の僧侶は皆家族。西だろうが東だろうが、助け合わねばなりませぬ。」
もはや、忠政は相手にする気にもならなかった。
「もうよい!この者らを引っ立てい!おって厳しく沙汰する!」
隠元が進み出、忠政も馬を下り、互いに礼を交わし合った。
通辞が側にくるまで、二人はしばし見つめ合い、思わず長いため息を漏らすのであった。
****** ****** ******
二人のため息が、重い建材を運ぶ威勢の良い掛け声に変わった。
雲南から運ばれてきた楠木の束がひとつ、またひとつと、地面に敷かれた丸木のころに乗り、徐々に山道の坂を上って行く。
材木を運ぶ男たちの掛け声が、青空に吸い込まれていく。
楠木の棟木や梁が三脚の支えで吊り上げられ、一本また一本、空に向かい立てられていく。
隠元禅師と范道生、そして大眉らは寺院建立の設計図を広げ、まもなく建設地にその姿を現わすであろう寺院の威容を思い描いては、心からの微笑みをもらすのであった。
第二十七話
隠元は、幼いころに戻れたかのような気分だった。憂いも迷いもなく、青空と白雲に向かい、どこまでも飛んでいけた。
思い切り上を向いて、高度を上げてから、気持ちよく滑空していくと、緑豊かな山腹に、黄金色に輝く萬福寺が見えた。
「阿昞(あびん)兄さん、阿昞兄さん」という、どこかで聞いたような懐かしい声が聞こえたような気がした。
山の坂道の黒い石の上で横になって休んでいた隠元が目を開けると、そこに、忘れがたい幼馴染(おさななじみ)の顔があった。年若いころに別れ、その後、戦乱の最中、束の間に一度きり再会していた阿梅!それは、夢幻などではなく、本当の黄幽梅だった。
隠元はいたく驚き、飛び起きて問うた。
「阿梅、どうして、ここに?」
黄幽梅は、すると、とめどなく涙を流し、声にならない声で、
「国が、滅びました。そして兄が…兄が、明のため…義を全うして亡くなったのです!」
後ろに立っていた鄭彪と何素如が急いで隠元に拝礼し、
「忠義の一門黄家は、いまやこの黄幽梅一人を残すのみとなりました」と言った。
隠元は、はげしい衝撃を受けた。
悲痛な思いを抑え、おもわず天を仰ぎ、呻(うめ)くように声を上げた。
「衆生の苦難、御仏は全てご存知だ。我が黄檗を興してこそ、天に報いることができよう。ああ、善き哉(かな)!」
黄幽梅はひとしきり泣いた後、涙を拭い、進み出て、傍らにいた朱虎を隠元に紹介した。
「尊師様、このお方は朱虎将軍です。兄と艱難を共にし、最期まで一緒でした。また、わたくしの命の恩人でもあります」
隠元が感激し、
「朱将軍に感謝いたします。生死の交わりは実に尊いものです」と言うと、朱虎は袖(そで)から一通の書状を取り出し、隠元に渡した。
「尊師様、これは軍師殿より託された物です。どうかお納めください」
隠元はこれを拝受し、封を切って見るが、ひとつの文字も見えない。
しかし、にわかに感嘆し、
「文字の無い白紙の書状。おお!これこそ「是が極まれば否、無の中に有あり」というもの。陰陽はめぐり、永遠に続く。黄道周よ、君は天下の奇才だ。その奇才がわたくしに絶唱を送ったのか!」
そう言うと、隠元は文字の無い書状を大切に胸元にしまい込むのだった。
****** ****** ******
寺院建立地から程近い太和山。鮮やかな緑に包まれている。草木が青々と茂ったその上に広がる青空と白雲は、高く、清らかに、果てしなく蒼穹へと連なっていた。
太和山の麓の静かな場所に、松や柏に囲まれた「白雲庵」がある。
黄幽梅は、すでに尼僧となっていた。
白雲庵での日々は規則正しく、祈りと読経の明け暮れである。
隠元は今日、黄道周の書簡を手に、庵の前にやって来たが、幽梅の読経の声を耳にするや、身を翻し、引き返した。
何歩も行かないところで、今度は庵から木魚の音が聞こえてきた。それはまるで、幼きころ、黄家の大きな桑の木の下で聞いた黄幽梅の笑い声のようであった。隠元が、しばし目を閉じる。
いくつかの画面が、二重写しになって、隠元の脳裏に蘇(よみがえ)る。
笑いながら、二人して桑の葉を採りに走った道。
亀の甲羅を撫でながら、陰陽を語った情景。
黄家の屋敷で、幽梅に男女の別を問いかけられた情景。
そしてこの異国の地で再会したときの涙…
隠元は長い間行ったり来たりをしているうち、手にした書状がどんどん重くなっていくような感じがした。
天を仰ぎ、深呼吸をし、また白雲庵に足を向けた。しかし、今度は迷いのない、確かな足取りであった。
幽梅は木魚を叩きながら、外から聞こえる足音に気付いていた。
耳を傾けてしばらく聞いているうち、頬が紅潮するのが自分でもわかった。
そして、小さな笑みをこぼした。
第二十八話
山城国宇治郡。
黄檗宗萬福寺開眼の式典が、いままさに始まろうとしている。
なにしろ、国を挙げての催しである。全国各地より主だった大名、高僧が参集し、大変な賑わいである。
菊の紋章を付けた一際(ひときわ)色鮮やかな籠が到着した。
籠の御簾がめくられ、後水尾法皇がゆっくりと歩み出てきた。
家綱と隠元らがこれを出迎え、法皇が席に着くのを待った。
やがて、会場全体に、万歳三唱が沸き起こった。
法皇は満面に笑みをたたえ、親しげに隠元と家綱にも左右に掛けるよう促した。そして、会衆に向かいよく通る声で述べた。
「本日盛典を催し、御仏(みほとけ)を仰げること、朕まことに喜びの極みである。日本国の法皇として、華(か)夏(か)(中国のこと)より参られた高僧隠元禅師に感謝したい。朕の願いはただ一つ、禅師より御仏のありがたい御言葉を授けていただき、万民に幸福がもたらされることである」
家綱、ここで、家臣に筆と硯を用意させた。
隠元は、恭しく法皇に拝礼したのち、
「法皇様の聖(せい)旨(し)は、万民に大いなる愛が注がれること。拙僧、ここに謹んでお祝いの気持ちを込め…」と言うなり、
法鏡交光 六根成慧日
牟尼真浄 十地起禅雲
の書を一気に書き上げたのであった。
隠元の両側におった二人の僧侶が、前に進み出てその書を掲げ、恭しく法皇にこれを見せた。法皇は目を輝かせて大いに喜び、朗々と読み上げた。
ふたたび万歳の声が、周囲の山々にこだました。
その夜はやや雲が掛かっていた。
そのうちに、その雲間より蒼い月光が射し込んで来て、寺院の仏像に薄銀色の羽衣を着せ掛けた。吉祥の光、であった。
第二十九話
寛文十三年(一六七三年)四月十三日。
萬福寺松隠堂。
黄昏が近かった。
髭も眉もすっかり白くなった隠元が病床に伏している。
木庵がそっと音を立てないよう禅師の傍に来て、にっこり笑うと一本の掛け軸を隠元に渡した。隠元は、それを開くよう頼んだ。
掛け軸が、ゆっくりと広げられる。
上のほうに書かれているのは、隠元が嘗(かつ)て仙巌で鄭成功に贈った「禅」の文字であった。最後の一筆をとりわけ長く伸ばしてしまったのをよく覚えている。
しかし、掛け軸を下のほうへ続けて開いていくと、その長い筆跡がもう一つの文字に繋がっているではないか。
それは、「神」という文字だった。
禅の字の縦の一筆と、下のほうに書かれた神の字の縦の一筆がちょうど一本で繋がっていた。
絶妙な構成であって、二文字がまるで一体を成していた。
この「禅神」の掛け軸を見て、隠元は一瞬目を輝かせ、手を震わせた。そして、低い声で、
「こ…これはどこから来たものか?」と尋ねた。
「鄭大将軍が人を遣わし、台湾から届けられました。天下の偉大な禅は神と共にあるとおっしゃいまして」
木庵が答えた。
隠元は、おだやかに微笑み、
「さすがは鄭成功殿じゃ。この一筆をつなげたのは神様であろう!」
隠元は突然何かを思い出し、無理のきかぬ身体ながら、なんとか手を伸ばし、枕辺からあの文字のない手紙を取り出し、蝋燭にかざして左右を見比べてみたり、あちこち触っていたりしたのだが、そのうち、封書から、干からびた蚕がポトリと落ちた。
「黄道周よ、この字のない書状には果たして「童心」まで込められていたのだね。蚕も死ぬまで糸を吐き続ける…」
隠元は、ここで、唐詩を詠んだ。
相見時難别亦難
東風無力百花残
春蚕到死糸方尽
蜡炬成灰泪始干
前の二句は、阿昺と阿梅が戦乱の中で、再び会いまみえるも、別れざるを得なかったときに詠まれたもの。そして後の二句は、隠元のいまこの瞬間の心境を託したものであった。
隠元は、震える両手で、干からびた蚕を封書に戻すと、
「木庵や、あとひとつ、頼まれてはくれぬか?」
「尊師よ、何なりと」
「これはの、われらが祖国、明国の蚕じゃ。故郷の蚕なんじゃ。これを、あの、上州は富岡の蚕農園に届けておくれ。記念としてじゃ。この国の養蚕が、ますます発展するようにな」
「承知仕りました。尊師よ、どうぞご安心ください!」
木庵は、隠元の遺言を心に刻んだ。
しかし、涙があふれてくるのをどうしようもなかった。
大眉と独立が、盆を捧げ、壷を下げ、日夜隠元に仕えている。
その日、隠元はまた、思うように動かぬ身体で枕元の亀を入れた竹籠を手に取り、独立に渡すと、小声でつぶやくように言った。
「独立よ。わたくしはこの亀を普陀山で拾って以来、今日まで数十年も一緒であった。そろそろ、これを山に帰してやっておくれ」
独立は涙を浮かべて頷き、竹籠を提げて出て行った。
隠元は、体を斜めに横たえ、弟子の行く先を見ている。
隠元の視線の先には、門外のすぐ近くにある「放生池」があった。
亀は、竹籠から這い出ると、首をひねってみせた。それはまるで、蝋燭の明かりを探しているかのようにもみえた。
隠元の傍らで、蝋燭の炎が揺らめいた。
隠元が微笑み、大儀そうに、亀に向かって手を振った。すると亀は、まるでその意を悟ったかのようにドボンと、水の中へ去って消えた。
池の水面に波が生まれ、瞬間、それは大海原へと変った。
隠元はまた、手で木庵を招き寄せ、木庵に寄りかかって足を動かし、文机の方をしきりに見た。木庵が目を凝らし、すぐさまあの未完成の書を見つけ出し、師匠の前に広げた。この時には、独立も放生池から隠元の傍に戻ってきていた。
隠元は頷くと、突然咳き込み、ゆっくりと、低い声で、
「遂に、その時が、訪れたようだ」
こう、言った。
木庵、大眉、独立は、師匠が臨終のことを言ったと即座に感じ取り、感極まり、涙をこぼし始めた。
隠元は、微笑んで、
「大の大人が、いい年をして、泣くのか?」と諭した。
そして、命の最後の力を引き出して、問うた。
「そなたたちに聞こう。いま、萬福寺はここ日本にいくつ建てられたか?」
大眉が即座に答える。
「一千百にも及びます!」
隠元が、再び問うた。
「僧侶と信徒はいかほどじゃ?」
大眉が再び答える。
「二千五百万人にも及びます!」
すると、隠元は、両の目をきらりと輝かせ、
「素晴らしい!黄檗よ、萬福よ!拙僧は老いぼれたが、山は老いることがない!」
そして、突然、弟子の制止もきかず、自ら筆をとり、あの未完成の大きな画仙紙に一気に力強く、「千山静」の三文字を書き加えんとした。
しかし、筆は床に落ち、墨が辺りに飛び散った。
夕日が西の空に沈み、山影がぼんやりと霞んでいた。
萬福寺の内外に、隠元の入寂(にゅうじゃく)近しと聞かされた無数の僧侶たちが粛然と立っている。
落日のなごりの光が、僧侶たちの悲しみを際立たせていた。
多くの者の目に、涙が光っていた。
やがて、寺院の奥にある松隠堂から、悲痛な叫び声が聞こえてきた。
「隠元禅師様が円寂なさった!阿弥陀仏!」
遥か遠くの夜の漆黒の中で、一筋の稲光がきらめいたかと思うと、ほどなく重苦しい春の雷が地を這うように迫ってきた。
雷は放生池をも揺るがし、波打つ池の水面から一匹の亀が頭を現し、金色の眼を光らせて周りを見回し、雷のわけを探っていた。
雷鳴が遠のくと、にわかに僧達の声が沸き起こった。
南無阿弥陀仏の斉唱が、いつまでも夜空に響き渡った。
****** ****** ******
朝日がゆっくりと昇り、紺色の世界から、暖色の世界へと、雲が次第に色づき始めていた。
萬福寺はその日、清新な陽光の下、ことのほか端正な姿に見えた。
寺の広大な敷地を取り巻き、弔いの旗がたなびいている。
白い幟に、全国各地の萬福寺の名が刺繍されていた。その範囲はまことに広く、山城(京都)のほか、九州、関西、関東、琉球、北海道など、実に一千にも及んでいた。
松隠堂の正門が開かれ、蓮の形の仏座が、僧達に担がれて静かに運び出され、境内に設(しつら)えられた精緻な造りの石塔にゆっくりと向かう。
石塔は香炉から立ち上る煙に囲まれ、蝋燭の炎が蓮の形の仏座の上で、まるで生きているかのように端座する隠元の亡骸をきらきらと照らしていた。
白い眉の下の、目を閉じた顔が優しい。両の手で囲うように持っているのは、長年使い込んで、飴色のツヤの出た竹製の禅杖であった。
僧達の祈祷が続く。
そのなかで隠元の亡骸が塔の中に移され、鐘が三回打ち鳴らされると、突如、塔の先端から白い霧が降りてきて隠元の体を包み込み、白玉の彫刻のようにみえた。そして再び三度鐘が鳴ると、六人の僧侶の手により重い石塔の門が厳かに閉じられた。
三度目の鐘の音が響きわたり、僧達は経文を唱えながら、列を成して前へ進み、再び松隠堂に入り、中堂の両側に並んだ。中堂には、隠元禅師の大きな肖像が掲げられていた。周囲の蝋燭の炎が、僧達の泪を照らしている。
隠元の肖像の傍らには、後水尾法皇直筆の「大光普照国師」という称号の軸が掛けられていた。そしてもう一方には、隠元の遺筆となった「孤旌独輝千山静」という力強い七文字が高く掲げられていた。
第三十話
その日は雲一つない、日本晴れであった。
新幹線「のぞみ」が、大地を飛ぶように疾走している。
気持ちの良い客車の中で、翔くんと麗ちゃんが車窓に映る夏景色を楽しんでいる。
今日は、特別な日であった。
かれらはおじいさんと三人で、夏休みの京都旅行に出掛けていたのだ。
なにしろ「隠元豆秘話」を聴いてから、初めての京都なのである。とにかく、早く物語に出てきた神秘的な場所、たとえば「放生池」とか「白雲庵」をこの目で見てみたい。そして、何より隠元禅師の亡骸が収められているというあの石塔。五十年ごとに新しい袈裟に着替えさせるというではないか。
麗ちゃんにとっては、そもそも京都自体が初めてだった。もちろん、萬福寺も初めてである。麗ちゃんはおじいさんと手を繋ぎ、お兄さんのバックパックを引っ張りながら、おそるおそる、立派な山門をくぐった。
いっぽうの翔くんは、以前にも来たことがあった。そこで妹を連れ、真っ先に入口から右手にある「放生池」に飛んでいった。
池は、蓮の葉でいっぱいだった。いまを盛りの蓮である。なんと美しい景色であろう!
だがそのおかげで、水面がさっぱり見えない。亀はここで放たれたはず。それなら、いったいどうやって大海に出れたの?彼岸にまで辿り着けたの?
おじいさんは、宝殿の右側に立ち、なにかをじっと見つめていた。
其処には、「黄檗樹」という表示が掛けられていた。
翔くんと麗ちゃんが駆け寄ってみると、果たして、いまにも倒れそうな一本の古木であった。
「黄檗樹の樹皮はね、病を癒し、人を救う、それは貴重な漢方薬の原料になったのだよ。もちろん、皮が無くなってしまっては、この樹も死んでしまうがね」
が、しかし、よく見ると、古木は新芽をふいていた。
(これはまた、どういうことなのだろうか)
宝殿に向かって左側に、隠元豆の豆棚があった。つややかな緑が、目に眩しい。そろそろまた、収穫の季節を迎えるのであろう。
麗ちゃんが、飛び跳ねるように豆棚の脇に駆け寄り、豆をひとつだけ捥(も)ぐと、ひと粒を口に入れ、つぎに、お兄さんにも味見させてみた。
「おいしい!」
都会で生まれ育った兄弟が、はじめて、大地の恵みの詰まった隠元豆のほんとうの美味しさを知った瞬間だった。
おじいさんは心に温かなものを感じながら、隠元の眠る石塔のほうを指し示し、そちらに行こうと手招きした。翔くんは、その道を憶えていた。振り返って、妹を呼ぶ。
だが、麗ちゃんは「遺骨」だなんて、思うだけでも怖かった。
突然回れ右をしたかと思うと、そのまま萬福寺を出て、白雲庵のほうに行ってしまった。
おじいさんは思わぬ展開に、息を切らしながら、「ははぁ、この子はとにかく梅ちゃんが気になって仕方がないのだな」と、むしろほほえましい気分になったのだった。
もう七、八年もすれば、また隠元禅師の五十年祭。そのころはそう、この子たちの時代になる。
麗ちゃんはといえば、京都に来る新幹線の車中、おじいさんが教えてくれた歌を思い出していた。ひとしきり走ったら、「白雲庵」の字がはっきり見えてきた。
小さく口ずさんでいた歌が次第に大きなコーラスになってきた。そう、それは、天から降りてくるような、素敵なコーラスだったのだ。
天外呀有青天,
白云之上,蓝呀蓝无边。
山外呀有青山,
绿荫之下,路呀路蜿蜒。
弯弯的小路通大道,
默默的脚印紧相连。
行善之道,无呀无尽头,
涅磐心经,念呀念不完。
天下僧侣,本属一家,
东来西去,救苦救难。
举步远,不如登高声声唤,
大爱无疆,大爱无疆!
放眼看,青峰何处最美艳?
山花烂漫,山花烂漫!
天の外に、青空あり
白雲浮かべ、藍はどこまでも藍
山の外に、青山あり
緑陰の下、小道が延々とつづく
曲がりくねった小道が大路へ通じ
黙々と辿った道もいつか重なる
善行の道は尽きることなし
涅槃心経は念じ終わることなし
天下の僧侶は ほんらい一家
東西行き交い 苦難に遭えば 互いに助け合う
遠くへ行くより、高みに登って呼びかけよう
大いなる愛永遠なれと、大いなる愛永遠なれと!
見渡せば 青い峰のどこが最も美しいと言えるのか?
山には花が咲き誇る こんもりあでやか咲き誇る!
完